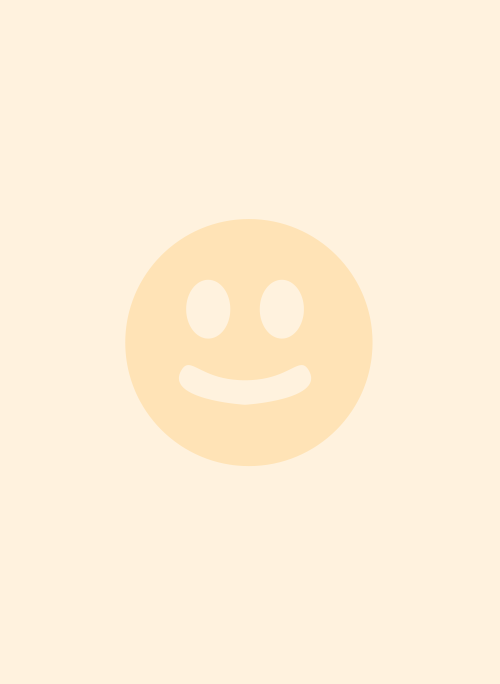午後の授業は、珍しく頭に入ってこなかった。
黒板の文字も線が重なっているだけのようにしか見えなくて、ノートに板書することすら忘れてしまっていた。
「橘さん、大丈夫?」
目の前に座る白河さんが覗き込んできた。
その心配そうな瞳に、あたしもようやく我に返る。
「え、あ…ごめん。ちょっとぼーっとしちゃって…」
なんとか笑って誤魔化すと、もう一度昼休みの出来事を思い出していた。
ベティが口にした名前。
リュウセイたちの本当の名前は珍しいから、その独特の響きを聞いてすぐわかった。
「リゲルも、いわゆる幼馴染さ」
寂しげに笑うベティにもなにかあるのだろう。
下唇をきゅっと結ぶと、ベティはあたしに向き直る。
「あんたとは正反対な女の子だよ。元気で明るくて、かなりお転婆だし…リゲルが笑うとみんな笑うんだ」
楽しそうにベティは微笑んでいて、そのときあたしはピンときた。
……ああ、ベティはその子に恋してるんだ。
切れ長の魅惑の瞳も、すべてはリゲルに向けられている。
こんなにも愛しそうに話すベティは、やっぱりリュウセイの友達なのだ。
「リュウセイは……」
黒板の文字も線が重なっているだけのようにしか見えなくて、ノートに板書することすら忘れてしまっていた。
「橘さん、大丈夫?」
目の前に座る白河さんが覗き込んできた。
その心配そうな瞳に、あたしもようやく我に返る。
「え、あ…ごめん。ちょっとぼーっとしちゃって…」
なんとか笑って誤魔化すと、もう一度昼休みの出来事を思い出していた。
ベティが口にした名前。
リュウセイたちの本当の名前は珍しいから、その独特の響きを聞いてすぐわかった。
「リゲルも、いわゆる幼馴染さ」
寂しげに笑うベティにもなにかあるのだろう。
下唇をきゅっと結ぶと、ベティはあたしに向き直る。
「あんたとは正反対な女の子だよ。元気で明るくて、かなりお転婆だし…リゲルが笑うとみんな笑うんだ」
楽しそうにベティは微笑んでいて、そのときあたしはピンときた。
……ああ、ベティはその子に恋してるんだ。
切れ長の魅惑の瞳も、すべてはリゲルに向けられている。
こんなにも愛しそうに話すベティは、やっぱりリュウセイの友達なのだ。
「リュウセイは……」