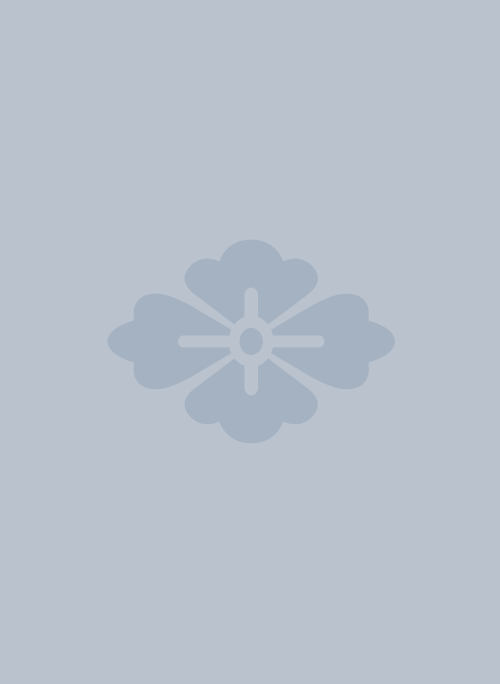幼い頃から奏の面影はあった。
日に透ける柔らかな髪。
長い睫毛に縁取られた丸い、大きな目。
滑らかな、頬。
まだ拙い喋りで『ととしゃま』と笑いかけてくるその顔は確かに彼女の娘なのだと思うことが出来た。
その成長が嬉しかった。
首に絡みつく手。
抱っことせがんだその小さな体はいつしか一人で通りを駆けるようになった。
七つの帯解き(七五三の七つの年に行う儀式)を済ませる頃には身の回りのことは殆ど自分で出来るようになった。
いつからか、母を求めて泣くことはなくなっていた。
それでも片親……しかも父しかいない彼女には苦労させたのだと思う。
辺りの子よりも明らかに大人びた彼女は不思議と言葉遣いまで母である奏に似ていった。
成長する程に彼女は母の面影を色濃くしてゆく。
明るく、優しく、そして真っ直ぐに育ってゆく彼女の向こうに奏を見た。
「父さま」
そう言って笑いかけてくる彼女に、今も愛しいその母が重なる。
忙しい日々に追われて仕舞い込んでいた鮮やかな感情が甦って。
俺は、彼女に手を伸ばした。
――奏。
「有り難う」
俺にこの子を遺してくれて。
俺達の元に産まれて来てくれて有り難う――
「……お礼を言うのは私の方です父さま」