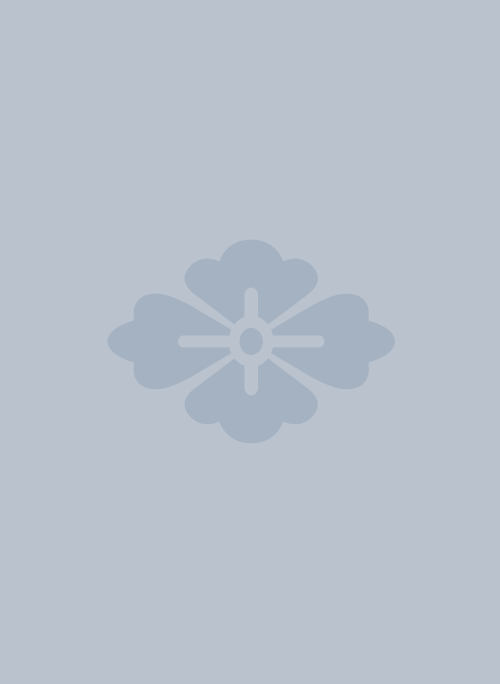「──わぁ凄い……!」
川辺に浮かぶ光の群れ。
一つ一つは小さな淡い光だというのに、真っ暗な水面にその身を映して数を増やした彼らの輝きはまさに圧巻だった。
あまり夜に出歩くことのなかった私はこんな数の蛍を見るのも初めてで、さっきまでとはまた違う喜びに頬が上がる。
「凄い!星みたいですっ!触れますかねっ!?」
「あー下りたら幾らでも寄って来んぞ」
朔月の今日、辺りはとても暗かった。
石や草に足を取られるのを、手を引く土方さんに助けられながらに河川敷に下り立つ。
これまで男として生きてきた私には、それがまた女として扱ってもらっているように思えて少し緊張する。
でもふわりと寄ってきた小さな蛍が袖に止まって。
すぐにそんな気持ちも霞んでしまった。
「止まりましたよ!凄い、ほら!」
どうすればこんなに綺麗に光るんでしょう。
ついたり、消えたり。
ゆっくりと内側から滲むように輝くそれはいつまで見てても飽きそうにない。
ほう、と微かに息を漏らしてじっと魅入る私の視界に、蛍を乗せた武骨な指が映る。