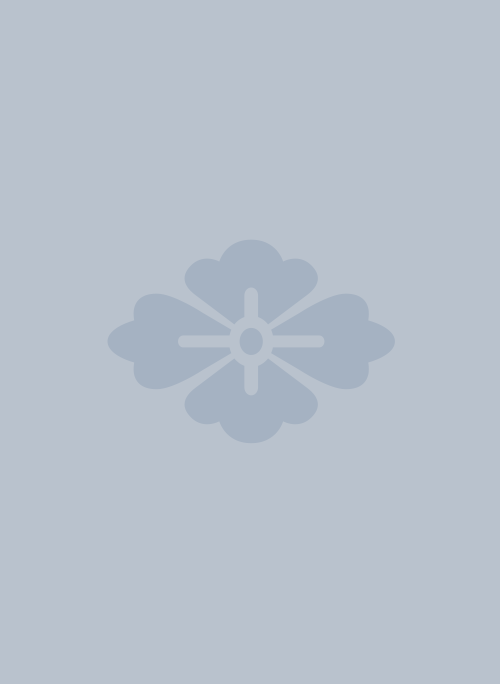「歩けますよ?」
「知っとる」
結局、そんな私の小さな抗議をさらりと流す山崎に連れられ部屋に入ると、脱け殻だった布団がすっかり冷えて私を迎える。
「お土産」
なのに不意に重なった唇から押し込まれた飴に、一気に体温があがる。
甘い不意打ち。
こんなの反則です……。
「……食べ掛けじゃないですか……」
「もうすぐ飯やろ、半分で我慢しぃ」
照れ臭くて思わず目を逸らした私の感情などすっかり見透かされているのか、山崎はお構いなしに頭を撫でてくる。
以前は子供扱いされているようで嫌だったそれも、いつの間にかその触れる体温に心が落ち着くようになっていて。
口の中に広がる飴の甘さのように、さっきまでの淋しさも、張っていた意地も、ふわりと柔らかく溶けていく。
「……有り難うございます。今度はちゃんと丸いまま下さい」
「ん、また明日な」
本当は。
この数日少し体調が悪くて食欲のなかった私を案じてのことなのだと思う。
何だかんだでこの人は優しいし、私のことを良くわかってる。
決して無理強いはしないけど、一見分かりにくいこの人の心配の仕方は、嫌いじゃなかった。
それを証明するように、単純な私は間違いなく半分この飴に浮かれていて。
今ちょっと、元気だ。