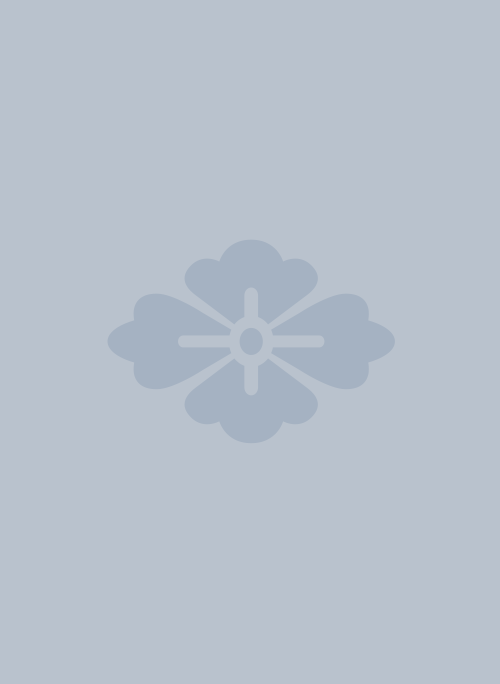訪れた沈黙に、風がカタカタと障子を揺らす音がいやに大きく聞こえた。
僅かに見開かれたその黒い双眸は何か迷っているようにも見えたけど、よくわからない。
普段あまり見たことのないその様子に一くんが抱えるものの大きさを感じて、気が引き締まる。
火鉢から伝わる仄かな熱がじわりと存在感を持つ中で、一くんは口許に微かな笑みを浮かべた。
淋しげな、笑みを。
「……なら、その言葉に甘えても良いか?」
「もっ、勿論ですよ!」
少しでも役に立てるのなら話なんて幾らでも聞きます!
とりわけ落ち着き大人びた一くんがそんなことを言ったのは初めてで。
これは余程の事に違いない。
そう思って返事にも力の入った私は、緊張で乾いた喉にごくりと唾を飲んだ。
一体何が……。
「……俺は、お前が大切だ」
「……え?」
けれど真剣な顔で紡がれたのは予期せぬ言葉で。
無意識にも声が漏れた。
なな、何を……っ!?
「俺だけじゃない、皆そう思ってる。本当ならこんな所じゃなく、別の場所で幸せを見つけて欲しいと思っている筈だ」
……ですよね。
一くんがそんな目で私を見る訳がない。早とちりも甚だしい馬鹿な勘違いに背が萎む。
火照った頬に益々熱が集まり、その恥ずかしさから顎を引いた私は顔にかかる髪を指で撫で梳いた。
しかしながら今更なその話はやはり腑に落ちなくて、モヤモヤとした気持ち悪さに唇が尖った。
何でまた──
「だから俺はお前の言葉で聞きたい。その体で此処に残るのは本当にお前の願いなのか?」