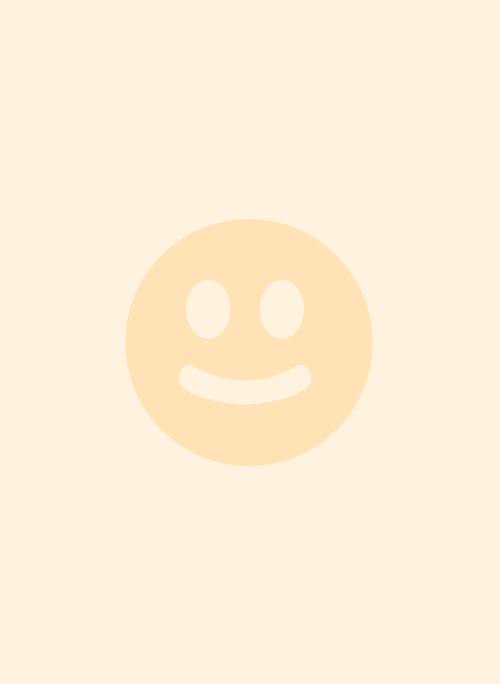「旭君。大好きっ」
隣から勢いをつけて旭君の胸に飛び込むと「危な……」って体を反り気味にしながらもしっかりと抱きとめて貰える安心感に顔が緩む、やっと好きって伝えることができた。
こんなに優しくて素敵な人を私は知らない。
その人が私を好きでいてくれる奇跡に感謝して、地中深くまで落ちていた気持ちが急浮上する。
『あぁーもうホントに好き、大好き。うん。大好きも超えて愛してる』
まだ声に出して言うのはとても恥ずかしい。
でも今まで気持ちを押さえていた分『好き』が洪水となって旭君の飲み込んでしまうかも知れない。
幾ら見つめ続けても見飽きる事の無い旭君の顔に朱がさしたのを目ざとく見つけて悪戯心に火が点いた。
「チュッ」
先程のお返しとばかりに、魅惑的な唇に自分からキスを仕掛ける大胆な行動に出た。
「うわぁ……なっ……」
良く分からない言葉を発して慌てる旭君をふふって笑いながら見つめていたら、
「はぁー」とまたしても旭君の深いタメ息が聞こえてきた。
「自分ちのリビングだから用心してたのに……火を付けたのこいちゃんだから覚悟してね」
シャイな感じから豹変し、カンナちゃんのような黒い笑顔を私に見せる旭君。
初めて目したその笑顔の衝撃で自分の顔が徐々に強張って行くのが分かる。
悪戯のつもりだったのに……
自ら手に余る状況を招いてしまったことに慌てふためく、
……が時既に遅し……