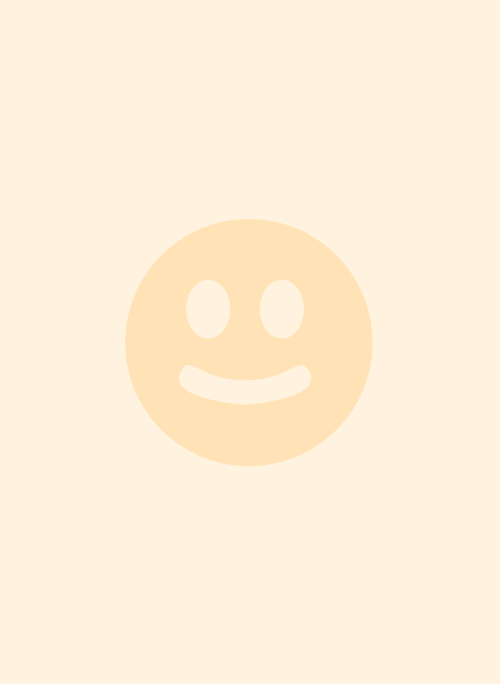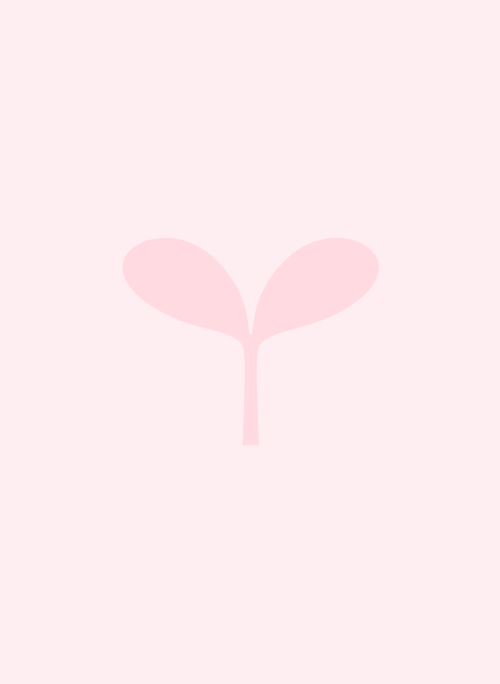馬鹿みたい。
簡単に彼は死んでしまった。踏切を渡ろうとした猫を助ける為に彼は死んでしまった。周りの人間がそれを聞けば、彼は素晴らしい人間だと思うでしょう?だけど、そんなことないわ。どうして今さら偽善の固まりのような行為をしたの?あんなにあんなにこの醜く汚い世界が嫌いだなんて言ってたくせに。どうして今さら猫なんかを助けたの?どうして、私達なんかより老い先短い猫なんかを助けたの?そればっかりが頭の中を巡るばっかりで私は泣ける筈もなかった。泣いたって仕方ないのが解っていたから。
静かに染み渡る夜。暗い森の広場では黒いスーツを着た二人の男と、同じく黒いシンプルドレスを着た女がいた。黒いシンプルドレスを着た女は泣崩れ、黒い黒い棺に縋りついていたし、男達は涙を流さないものの、悔しそうに唇を噛み締めていた。私は彼等から離れた場所に、ただ立っていただけ。私は、マリアのように綺麗な涙を零すことは出来ないんだろうな。
「嗚呼……グイード……グイード…」
「マリア……泣かないで。…仕方ないんだ。グイードだって僕らだっていつかは死んでしまうのだから」
そっと棺に泣き付くマリアの肩を抱くシェイドだって目が潤んでるよ。
「仕方ないなんて簡単に言わないでよ…!」
気がつけば私は叫んでた。嫌だな、私のこの素直になれない歪んだ性格は愛しい人のお別れ式までぶち壊しちゃうのか。
「…キール」
マリアが哀しそうな顔をして私に近付いて私の肩に手を置こうとした。私の名前を呼ばないで、呼んでいいのは彼だけよ!ほら、醜い私は止まらない。
パンッという鋭い音を立てて、私の手が彼女の手を阻む。私だってマリア達と同じように哀しい。悲しくて一人で立つのが精一杯で誰かに慰めて欲しい筈なのに、それさえも私の醜い性格が許さない。
私は、いつだってそうだった。この性格だから友達も出来ないで、ずっと孤独だった。そんな私に唯一、手を差延べてくれたのがグイードだったのに。
―… 僕は貴方を愛しています。
それすらも嘘だったの?だって彼は私の元を離れて行ってしまったのだから。
簡単に彼は死んでしまった。踏切を渡ろうとした猫を助ける為に彼は死んでしまった。周りの人間がそれを聞けば、彼は素晴らしい人間だと思うでしょう?だけど、そんなことないわ。どうして今さら偽善の固まりのような行為をしたの?あんなにあんなにこの醜く汚い世界が嫌いだなんて言ってたくせに。どうして今さら猫なんかを助けたの?どうして、私達なんかより老い先短い猫なんかを助けたの?そればっかりが頭の中を巡るばっかりで私は泣ける筈もなかった。泣いたって仕方ないのが解っていたから。
静かに染み渡る夜。暗い森の広場では黒いスーツを着た二人の男と、同じく黒いシンプルドレスを着た女がいた。黒いシンプルドレスを着た女は泣崩れ、黒い黒い棺に縋りついていたし、男達は涙を流さないものの、悔しそうに唇を噛み締めていた。私は彼等から離れた場所に、ただ立っていただけ。私は、マリアのように綺麗な涙を零すことは出来ないんだろうな。
「嗚呼……グイード……グイード…」
「マリア……泣かないで。…仕方ないんだ。グイードだって僕らだっていつかは死んでしまうのだから」
そっと棺に泣き付くマリアの肩を抱くシェイドだって目が潤んでるよ。
「仕方ないなんて簡単に言わないでよ…!」
気がつけば私は叫んでた。嫌だな、私のこの素直になれない歪んだ性格は愛しい人のお別れ式までぶち壊しちゃうのか。
「…キール」
マリアが哀しそうな顔をして私に近付いて私の肩に手を置こうとした。私の名前を呼ばないで、呼んでいいのは彼だけよ!ほら、醜い私は止まらない。
パンッという鋭い音を立てて、私の手が彼女の手を阻む。私だってマリア達と同じように哀しい。悲しくて一人で立つのが精一杯で誰かに慰めて欲しい筈なのに、それさえも私の醜い性格が許さない。
私は、いつだってそうだった。この性格だから友達も出来ないで、ずっと孤独だった。そんな私に唯一、手を差延べてくれたのがグイードだったのに。
―… 僕は貴方を愛しています。
それすらも嘘だったの?だって彼は私の元を離れて行ってしまったのだから。