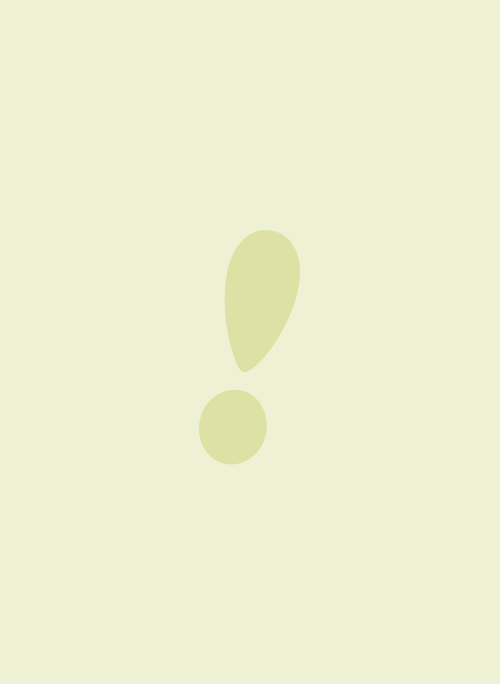マサ君は、ハッキリ言ってとびっきりのイケメンだ。
スッと通った鼻梁とサラサラの肌。少しつりあがった黒い瞳はとても色っぽい。
なんの手入れもしていないはずなのにその髪の毛はいつもサラサラで、細身なのに筋肉質な身体も腰にクるような低い声も、なにもかもがパーフェクト。
なのだが。
「いっつも黒い服ばっかり着てるし、無愛想だし人見知りだし全然表情変えないし!それで怖がられてお客が逃げてちゃ意味ないでしょうよっ!」
私はムッ、と口を歪めながら、図書館の外へと出た。
そもそも探偵というのは、お客さんからもらう1本の電話から仕事が始まるのだ。
なにか困った時にふと存在を思い出してもらうこと。電話をかけてもらうこと。
そしてそこで親身になって話を聞き、やっと仕事を任せてもらえるかどうかが決まる。
逆に言えば探偵は、そういった『営業力』がなければ仕事すら始められない可能性だってあるのだ。
そして、その『営業力』というものが潔いほど一切ないのが私の同居人であり探偵・マサ君なのである。