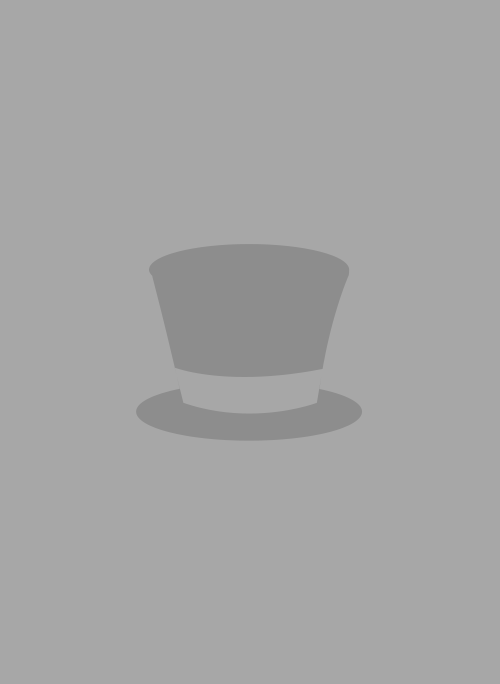これだけ暑ければ、車の中もかなりの温度になってるだろう。
僕はリエに待つように言うために振り向いた。
確かにかなりの勢いで、しかも急に振り向きはしたが、そこまで近くにリエがいるとは思っていなかった。
もう、ほとんど後にペッタリ引っ付くように、リエは僕の後ろに立っていた。
僕は、下から覗き込む大きな瞳と、僕のシャツに残念ながら届かなかった胸の先端に驚いて思わず後へ飛び退った。
僕は肘をガラス扉に打ちつけながら、リエの睫毛が意外に少ない事に気がついた。
店のガラス扉は鈍い音を立て、反動で僕をリエの方へ押し戻す。
レジを叩く店員が驚いてこちらを見たが、ガラス扉の無事を目で確認すると、またレジ作業へと戻った。
リエは僕を支えようと手を前に出してくれたが、僕は寸でのところで踏みとどまった。
「あぶないなあ」
リエは、少しだけ寂しそうに笑った。
僕を助けようと差し出された手はそのままの位置で、僕の腰の辺りを抱くような格好で固定されている。
僕を抱きとめることのなかった、宙に浮いたままのその手も、少しだけ寂しそうだった。