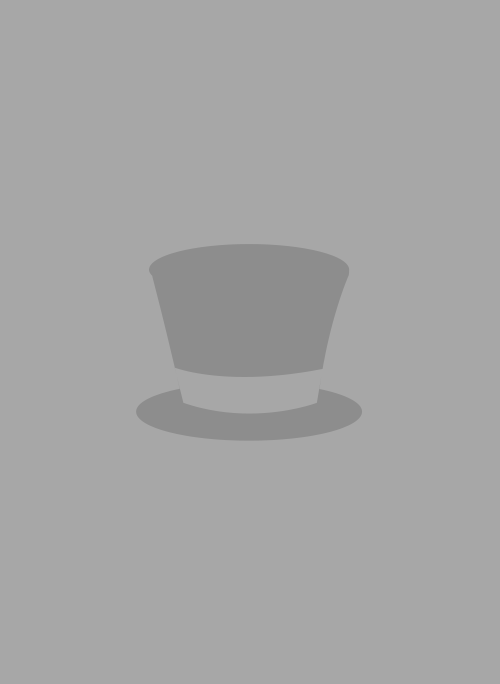普段、恋愛に関して奥手な僕が、先輩にだけこういう軽口を叩けるのには理由があった。
先輩は僕にとって、いわゆる『高嶺の花』なのだ。
その花はあまりにも高所に咲いていた為、僕なんか一度もそれを取りにいこうと考えたことすらなかった。
当然、相手がそういう対象で僕を見ることなんて、ありえないどころか夢にも思ったことがなかった。
だからこそ、いい意味で恋愛対象に見てなかったし、そこには駆け引きも存在しないから、キレイでかわいくて、白くて柔らかな存在を、ただ、からかって喜んでいたんだと思う。
「僕、一応、選ばれてんですよ」
「知ってるよ〜」
「バリっと投げますから、見ててくださいね!」
「うん♪」
「先輩の為に投げますから! ……愛を込めてね!」