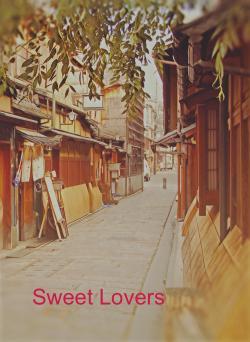秋山くんの話に聞き入ってしまって、コーヒーはすっかり冷めてしまっていた。
話を聞いて、私と拓実くんは、口をあんぐりさせるしかなかった。
秋山くんと深月は、何と中学の同級生だったらしい。
深月は当時から、カウンセラーをしていた母の影響で、心理学に詳しかった。
彼女は、上手く思ったような点数が取れない友人に、効率の良い勉強方法を考え、教えていたという。
しかも、認知心理学や発達心理学の知識を専門的すぎない言葉で説明しながら。
友人たちに、効果があったら教えてほしい
と言い添えていたという。
当時から大学の教授をしていた母の研究データを検証する手伝い役も担っていたはずだ。
それはあくまでも秋山くんの推測だった。
「当時は、俺もガキだった。
今よりもっと、アイツの、深月のこと、気になってたくせに。
心理学、心理学うるせーよー!
ガリ勉オンナー!
そう言ってからかうことで、アイツの気を引くことしか、できなかった。
アイツも、戸惑ってたよ。
俺とどう接したらいいか、わからなかったんだろうな。
俺もアイツも、お互いどう接したらいいかなんてわからないまま、あの日が来た。
……忘れもしない、中学3年の夏のことだ。
アイツは、いじめの兆候によく気付く聡い奴だった。
いじめられていたやつを何とかいじめから救おうと、教頭や校長まで巻き込んで。
自分の母親にも、被害に遭っていた子の両親にも協力してもらった。
そうやって器用に立ち回っていたんだ。
だけどその甲斐なく、そのいじめられていた子は屋上から身を投げて自ら命を絶ったんだよ。
……アイツの、深月の目の前で、な。
たまたま、アイツは正瞭賢高等学園の推薦入試の面接練習で学校に来ていたんだ。
普段は開いていない屋上のカギが開いていた。
そこで悪い予感がして、ドアを開けたらしい。
そういうとこ、周囲の人や物の様子がいつもと違うとこ、気付いちまうんだよな、アイツは。
それが、いいところでもあるんだけど」
秋山くんは、そこで言葉を切った。
いじめの兆候によく気がつくのは、私も身をもって知っている。
拓実くんが止めるのも構わずに、自分がいじめられた経緯を話すした。
肋骨骨折で、2ヶ月入院していたことも含めて。
その話をすると、秋山くんはため息を含んだ微笑を見せて、言ってくれた。
「はは。
変わってねぇのな、アイツらしいよ。
で、話の続きだ。
屋上を出て、階段の踊り場があるんだ。
そこで、アイツが、ちょうどさっきの理名ちゃんみたいな具合でぶつかってきた。
泣いてるんだよ、アイツ。
花藤 明日翔。
それがその子の名前だ。
身を投げた親友の名前を呼びながら、泣きじゃくってたよ。
さすがに、泣いてる女を放っておく趣味はないから、さ。
黙れって。
……ブサイクな泣き顔、見られたくねーだろ。
俺も見たくねーし。
そう憎まれ口叩いて、アイツの華奢な身体抱き寄せて泣かせてやった。
そのまま寝ちまったから、両親と姉貴に無理言って、俺の家に泊まらせたオチがついてるけどな」
何も言えなかった。
何も言ってはいけない気がした。
深月が。
中学生という幼い年齢で、しかも自分の目の前で。
親友を亡くしていたなんて。
私がいじめに遭っているときに、図らずも、当時いじめられていた子と私をオーバーラップさせてたりしなかったのだろうか。
彼女がフラッシュバックを起こしたところも、私は見ていない。
学校にいなかった期間のほうが長かったから、私が知らないだけなのかもしれないが。
「そんな様子、微塵も見せなかったな。
深月ちゃん。
俺がちゃんと関係切らなかった元カノがストーカーに豹変しやすい粘着気質だって、心理学の本までコピーして皆に解説してたし」
拓実くんからその様子を聞いて、秋山くんは爆笑していた。
「ほんと、変わってねぇのな!
その絵面、しっかりイメージできるわ。
目ぇキラキラさせて語って、ちょっとドヤ顔になってるんだよな。
そういう時のアイツの顔」
「でも、だからこそ。
普段は気丈に振る舞っているだけなのかもしれないな。
結構キツいんだぜ?
抱えているものを気兼ねなく吐き出せる相手がいないって。
しかも、彼女の場合は、自分がしっかりしていなかったから、親友が命を絶ったって、思っていそうな節があるし。
自分の弱い一面を見せられる、道明くんみたいな相手が、彼女には必要なんだろ。
彼女も、どっかしらで君のことは信頼していたんじゃないかな。
態度に出さなかっただけで。
じゃなかったら、道明くんに身体預けて泣いたりしないよ」
拓実くんの的確なアドバイスを、私はお人形みたいに隣で聞いているしかなかった。
店員さんが、冷めたコーヒーのおかわりをくれた。
カフェでの食事代金は2人が私の分まで払ってくれたのだった。
そして、私の自宅の最寄り駅まで2人はついてきてくれた。
私が改札を通るまで、見送ってくれていたのだった。
話を聞いて、私と拓実くんは、口をあんぐりさせるしかなかった。
秋山くんと深月は、何と中学の同級生だったらしい。
深月は当時から、カウンセラーをしていた母の影響で、心理学に詳しかった。
彼女は、上手く思ったような点数が取れない友人に、効率の良い勉強方法を考え、教えていたという。
しかも、認知心理学や発達心理学の知識を専門的すぎない言葉で説明しながら。
友人たちに、効果があったら教えてほしい
と言い添えていたという。
当時から大学の教授をしていた母の研究データを検証する手伝い役も担っていたはずだ。
それはあくまでも秋山くんの推測だった。
「当時は、俺もガキだった。
今よりもっと、アイツの、深月のこと、気になってたくせに。
心理学、心理学うるせーよー!
ガリ勉オンナー!
そう言ってからかうことで、アイツの気を引くことしか、できなかった。
アイツも、戸惑ってたよ。
俺とどう接したらいいか、わからなかったんだろうな。
俺もアイツも、お互いどう接したらいいかなんてわからないまま、あの日が来た。
……忘れもしない、中学3年の夏のことだ。
アイツは、いじめの兆候によく気付く聡い奴だった。
いじめられていたやつを何とかいじめから救おうと、教頭や校長まで巻き込んで。
自分の母親にも、被害に遭っていた子の両親にも協力してもらった。
そうやって器用に立ち回っていたんだ。
だけどその甲斐なく、そのいじめられていた子は屋上から身を投げて自ら命を絶ったんだよ。
……アイツの、深月の目の前で、な。
たまたま、アイツは正瞭賢高等学園の推薦入試の面接練習で学校に来ていたんだ。
普段は開いていない屋上のカギが開いていた。
そこで悪い予感がして、ドアを開けたらしい。
そういうとこ、周囲の人や物の様子がいつもと違うとこ、気付いちまうんだよな、アイツは。
それが、いいところでもあるんだけど」
秋山くんは、そこで言葉を切った。
いじめの兆候によく気がつくのは、私も身をもって知っている。
拓実くんが止めるのも構わずに、自分がいじめられた経緯を話すした。
肋骨骨折で、2ヶ月入院していたことも含めて。
その話をすると、秋山くんはため息を含んだ微笑を見せて、言ってくれた。
「はは。
変わってねぇのな、アイツらしいよ。
で、話の続きだ。
屋上を出て、階段の踊り場があるんだ。
そこで、アイツが、ちょうどさっきの理名ちゃんみたいな具合でぶつかってきた。
泣いてるんだよ、アイツ。
花藤 明日翔。
それがその子の名前だ。
身を投げた親友の名前を呼びながら、泣きじゃくってたよ。
さすがに、泣いてる女を放っておく趣味はないから、さ。
黙れって。
……ブサイクな泣き顔、見られたくねーだろ。
俺も見たくねーし。
そう憎まれ口叩いて、アイツの華奢な身体抱き寄せて泣かせてやった。
そのまま寝ちまったから、両親と姉貴に無理言って、俺の家に泊まらせたオチがついてるけどな」
何も言えなかった。
何も言ってはいけない気がした。
深月が。
中学生という幼い年齢で、しかも自分の目の前で。
親友を亡くしていたなんて。
私がいじめに遭っているときに、図らずも、当時いじめられていた子と私をオーバーラップさせてたりしなかったのだろうか。
彼女がフラッシュバックを起こしたところも、私は見ていない。
学校にいなかった期間のほうが長かったから、私が知らないだけなのかもしれないが。
「そんな様子、微塵も見せなかったな。
深月ちゃん。
俺がちゃんと関係切らなかった元カノがストーカーに豹変しやすい粘着気質だって、心理学の本までコピーして皆に解説してたし」
拓実くんからその様子を聞いて、秋山くんは爆笑していた。
「ほんと、変わってねぇのな!
その絵面、しっかりイメージできるわ。
目ぇキラキラさせて語って、ちょっとドヤ顔になってるんだよな。
そういう時のアイツの顔」
「でも、だからこそ。
普段は気丈に振る舞っているだけなのかもしれないな。
結構キツいんだぜ?
抱えているものを気兼ねなく吐き出せる相手がいないって。
しかも、彼女の場合は、自分がしっかりしていなかったから、親友が命を絶ったって、思っていそうな節があるし。
自分の弱い一面を見せられる、道明くんみたいな相手が、彼女には必要なんだろ。
彼女も、どっかしらで君のことは信頼していたんじゃないかな。
態度に出さなかっただけで。
じゃなかったら、道明くんに身体預けて泣いたりしないよ」
拓実くんの的確なアドバイスを、私はお人形みたいに隣で聞いているしかなかった。
店員さんが、冷めたコーヒーのおかわりをくれた。
カフェでの食事代金は2人が私の分まで払ってくれたのだった。
そして、私の自宅の最寄り駅まで2人はついてきてくれた。
私が改札を通るまで、見送ってくれていたのだった。