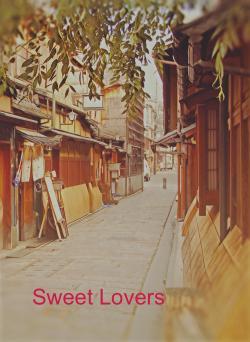翌日、洗顔を済ませようと1階に降りた。
我ながらよく眠れたものだとまだハッキリしない頭で考えた。
そして、父はいつの間にかソファーでいびきをかいて寝ていた。
いつの間に帰宅していたのだろう。
知る由もない。
知りたくもない。
無視を決め込む。
自分の父親に声も掛けないまま、冷たい水で洗顔を終える。
まだ腫れぼったい目元を隠すように、無理やりアイメイクを施す。
化粧が上手くのらなかったのを誤魔化すため、いつもは黒縁だが、赤いフレームの眼鏡をかける。
制服のブレザーを手に持つとローファーのかかとを踏んだまま、走って最寄り駅に向かった。
時刻は朝7時30分を回ったところだ。
電車に乗ると、通勤ラッシュですし詰めの車内に無理やり乗り込んだ。
こうして、四方八方からの人の圧力に耐えるほうが、まだいい。
二日酔いの父と話しながら朝食を胃に流し込むよりはマシだ。
学校の門をくぐり、昇降口で上靴を履き、教室のドアを開けた。
登校時間より1時間早いために当然ながら人はまだいない。
スカートが乱れるのなんて気にもせずに、ドカっと椅子に座ってコンビニで買ったパンにかじりつきながら、ぼんやり外を眺めた。
1人は楽だ。
誰にも干渉されずに済む。
だけど、昨日、仲良く話した子のことが頭に浮かんだ。
いっそのこと、彼らに洗いざらい喋ってしまいたいとさえ思った。
……母が亡くなったこと、今は父子家庭となっていること。
医者か看護師を目指していること。
話してしまえば、抱え込む必要もなくなる。でも昨日仲良くなったばかりの人に、いきなり重い話をされるのは、荷が重いだろうか。
そんなことを考えていると、パンを食べたことでようやく動き出した脳が、フリーズしたらしい。
私も、考えることに疲れてきて、組んだ腕を枕のようにして机に突っ伏した。
「あれ、理名ちゃんじゃん。
早くね?」
突っ伏してから、3秒も経っていない。
聞き覚えのある、低い落ち着いた声がした。
教室のドアを開ける音など、全く聞こえなかった。
まさか、ずっと、そこにいたの?
ゆっくり首を右にひねって、声のした方に目線をやった。
「よっ」とでも言いたげに、爽やかに片手をあげている麗眞くんがいた。
「おはよ」
彼に悟られないよう、俯いて挨拶を返した。
それなのに、 彼は初めて会った日と同じように私の顔を覗き込んだ。
「ね、理名ちゃん?
なんかあった?
目が腫れてる」
「大丈夫。
なにも、ないから……」
ここにいるのは友達だ。
親ではない。
それなのに、何でこんなに意地を張っているんだろう、私は。
意地を張る必要なんてないはずなのに。
自分の意地っ張り度合いには、呆れてものも言えない。
それにしても、麗眞くんはなんで、大丈夫じゃないことが分かるのだろう。
特殊能力でも持っているのか。
いや、医学的に、そんな能力は存在しない。
きっと、麗眞くんの勘なのだろう。
人の第6感は時にとても鋭いというのを昔、母の部屋だったか、学校の保健室にあった本で読んだことをおぼろげながら記憶している。
「ほんとに?
そう言う人に限って、大丈夫じゃないんだよ」
困ったように眉を下げて、所在なさげに頭を搔く彼。
耐えかねたのか耳元で囁くような声で、確かにこう言った。
「……理名。
泣いてる顔、俺見ないから。
泣いていいよ?」
親以外の人から、初めて名前を呼び捨てされた。
その言葉に、感覚に。
本能が反応したのだろうか。
グレープフルーツと、シトラスの香りが交互に私の嗅覚を刺激した。
それを感じた時には、もう既に私は麗眞くんの腕の中にいた。
誰もいないのをいいことに、声を押し殺して泣いた。
人前で泣くのは、何年ぶりだろうか。
昔から転んでも泣かない子だった私は、"我慢強い子ね"なんて母に褒められた、遠い昔を思い出していた。
いつの間にか、嗚咽を漏らしながら泣いている自分がいた。
こんなに泣いたのは、幼少期、公園で両親とはぐれたときに泣いたこと。
それに、母との、最後のお別れの時くらいだったと記憶している。
麗眞くんは終始、私が落ち着くまで、私の頭を撫でてくれていた。
ずっと私の頭を撫で続けて、腕も疲労を感じているはずなのに、疲れた様子は見せていない。
そのときだった。
教室の外で、一瞬止まった足音が、すぐにまた遠ざかっていった。
我ながらよく眠れたものだとまだハッキリしない頭で考えた。
そして、父はいつの間にかソファーでいびきをかいて寝ていた。
いつの間に帰宅していたのだろう。
知る由もない。
知りたくもない。
無視を決め込む。
自分の父親に声も掛けないまま、冷たい水で洗顔を終える。
まだ腫れぼったい目元を隠すように、無理やりアイメイクを施す。
化粧が上手くのらなかったのを誤魔化すため、いつもは黒縁だが、赤いフレームの眼鏡をかける。
制服のブレザーを手に持つとローファーのかかとを踏んだまま、走って最寄り駅に向かった。
時刻は朝7時30分を回ったところだ。
電車に乗ると、通勤ラッシュですし詰めの車内に無理やり乗り込んだ。
こうして、四方八方からの人の圧力に耐えるほうが、まだいい。
二日酔いの父と話しながら朝食を胃に流し込むよりはマシだ。
学校の門をくぐり、昇降口で上靴を履き、教室のドアを開けた。
登校時間より1時間早いために当然ながら人はまだいない。
スカートが乱れるのなんて気にもせずに、ドカっと椅子に座ってコンビニで買ったパンにかじりつきながら、ぼんやり外を眺めた。
1人は楽だ。
誰にも干渉されずに済む。
だけど、昨日、仲良く話した子のことが頭に浮かんだ。
いっそのこと、彼らに洗いざらい喋ってしまいたいとさえ思った。
……母が亡くなったこと、今は父子家庭となっていること。
医者か看護師を目指していること。
話してしまえば、抱え込む必要もなくなる。でも昨日仲良くなったばかりの人に、いきなり重い話をされるのは、荷が重いだろうか。
そんなことを考えていると、パンを食べたことでようやく動き出した脳が、フリーズしたらしい。
私も、考えることに疲れてきて、組んだ腕を枕のようにして机に突っ伏した。
「あれ、理名ちゃんじゃん。
早くね?」
突っ伏してから、3秒も経っていない。
聞き覚えのある、低い落ち着いた声がした。
教室のドアを開ける音など、全く聞こえなかった。
まさか、ずっと、そこにいたの?
ゆっくり首を右にひねって、声のした方に目線をやった。
「よっ」とでも言いたげに、爽やかに片手をあげている麗眞くんがいた。
「おはよ」
彼に悟られないよう、俯いて挨拶を返した。
それなのに、 彼は初めて会った日と同じように私の顔を覗き込んだ。
「ね、理名ちゃん?
なんかあった?
目が腫れてる」
「大丈夫。
なにも、ないから……」
ここにいるのは友達だ。
親ではない。
それなのに、何でこんなに意地を張っているんだろう、私は。
意地を張る必要なんてないはずなのに。
自分の意地っ張り度合いには、呆れてものも言えない。
それにしても、麗眞くんはなんで、大丈夫じゃないことが分かるのだろう。
特殊能力でも持っているのか。
いや、医学的に、そんな能力は存在しない。
きっと、麗眞くんの勘なのだろう。
人の第6感は時にとても鋭いというのを昔、母の部屋だったか、学校の保健室にあった本で読んだことをおぼろげながら記憶している。
「ほんとに?
そう言う人に限って、大丈夫じゃないんだよ」
困ったように眉を下げて、所在なさげに頭を搔く彼。
耐えかねたのか耳元で囁くような声で、確かにこう言った。
「……理名。
泣いてる顔、俺見ないから。
泣いていいよ?」
親以外の人から、初めて名前を呼び捨てされた。
その言葉に、感覚に。
本能が反応したのだろうか。
グレープフルーツと、シトラスの香りが交互に私の嗅覚を刺激した。
それを感じた時には、もう既に私は麗眞くんの腕の中にいた。
誰もいないのをいいことに、声を押し殺して泣いた。
人前で泣くのは、何年ぶりだろうか。
昔から転んでも泣かない子だった私は、"我慢強い子ね"なんて母に褒められた、遠い昔を思い出していた。
いつの間にか、嗚咽を漏らしながら泣いている自分がいた。
こんなに泣いたのは、幼少期、公園で両親とはぐれたときに泣いたこと。
それに、母との、最後のお別れの時くらいだったと記憶している。
麗眞くんは終始、私が落ち着くまで、私の頭を撫でてくれていた。
ずっと私の頭を撫で続けて、腕も疲労を感じているはずなのに、疲れた様子は見せていない。
そのときだった。
教室の外で、一瞬止まった足音が、すぐにまた遠ざかっていった。