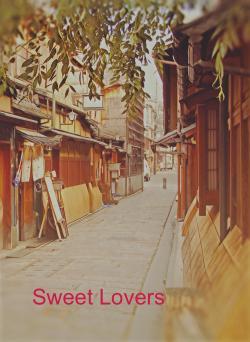そして、深月の様子であったり、得た情報を逐一共有する時間が毎週必ず、設けられた。
宝月家の使用人からの情報は、麗眞くんや相沢さんから伝えられることになっている。
場所はいつも宝月家邸宅だ。
「やっぱり、心理学を学んでいるからか、塾内の試験の成績がいつもトップなんだ。
それで、反感を買われている。
いじめの原因はどうやらそれであるらしい」
「潜入させている、宝月家の使用人からの情報です。
塾講師側も、いじめを見て見ぬフリをしているようです。
面接の際に聞き出しました。
『ウチの講師陣は8割が医大生。
忙しい合間を縫って授業をしてくれている。
それなのに、教え方にアドバイスの皮を被った文句を言ってくる、女子生徒がいます。
そういう問題のある生徒への対応もお願いしますが、大丈夫ですか。
まぁ、そういう生徒はいじめを受けたりして勝手に辞めていくので、ウチも気にしません』
そう、真顔で申していたそうです。
潜入させた使用人自ら、
『講師になることで、犯罪の片棒を担ぐことは教員免許を所持している身としては誠に遺憾です。
よって、この場で面接を打ち切らせていただきます』
こう啖呵を切り、件の塾講師になることを拒否した、というオチがございます」
「授業の流れを止めないように気を付けて、
授業終わりに『こう教えると、生徒のモチベーションが上がるアドバイス』をしているらしいんだ。
まぁ、高校生の癖に生意気だって思われるんだろうな。
大体、塾の講師をやっている人は大学生が多いから」
拓実くんの言葉に、反応したのは秋山くんだ。
「ほんと、変わらねーな。
中学校でもそんなだったよ、アイツ。
……教師陣に授業のフィードバックを進んでやるようなやつだった。
それで、経験の少ない新米教師とも馴染んでいたところがあったな。
教師のような年上の人とも、臆せずコミュニケーションが取れる人ですって通知表に書かれていたってことを、本人が言っていたよ」
来る日も来る日も、この状況を何とかするにはどうやって対処をしたらよいか、話し合った。
良い策なんて、高校生が考えることには限界があった。
何も出来ることはないんじゃないか、そんな空気が場を支配することも度々で、皆が途方に暮れた。
そんな空気を破ったのは華恋だった。
「もう去年のことになるけど、中学生の時にからかっていたっていう男の子の話題、多分今となっては道明くんのことだってわかるんだ。
それを深月の前で出したの。
彼女の中でそのことが、トラウマになっていたのに、気付けなかった。
彼女の気分を害してしまったの。
調子に乗ってたところもあった。
親友だから何でも、秘密とかなしで話してくれるはずだって。
話したくないこともあるんだって、そんなことにも気が付かなかった。
だけど、深月がこんな目に遭っているのを見たら、放っておくなんてできなくて。
今はちょっと喧嘩しちゃってるけど、気まずいけど。
ちゃんと深月に謝りたい。
そのためにも、深月を救わなきゃ。
明るい深月に、おはようって言いたいし、笑いかけてほしいの。
だから、皆も部活で忙しいのは分かっているけれど、協力してほしい!」
華恋の訴えに、皆が目線を合わせて、頷いた。
「アイツ、いい友達を持ったな。
俺からも、頼む。
アイツとは、高校も違うから、側にいて守ってやれない。
それが、すごい心苦しいんだ。
俺の分まで、アイツを、深月をよろしく頼む」
秋山くんまで、私たちに頭を下げる。
深月を救う。
そんな思いで一致団結した、そんな矢先に、悲劇は起きた。
宝月家の使用人からの情報は、麗眞くんや相沢さんから伝えられることになっている。
場所はいつも宝月家邸宅だ。
「やっぱり、心理学を学んでいるからか、塾内の試験の成績がいつもトップなんだ。
それで、反感を買われている。
いじめの原因はどうやらそれであるらしい」
「潜入させている、宝月家の使用人からの情報です。
塾講師側も、いじめを見て見ぬフリをしているようです。
面接の際に聞き出しました。
『ウチの講師陣は8割が医大生。
忙しい合間を縫って授業をしてくれている。
それなのに、教え方にアドバイスの皮を被った文句を言ってくる、女子生徒がいます。
そういう問題のある生徒への対応もお願いしますが、大丈夫ですか。
まぁ、そういう生徒はいじめを受けたりして勝手に辞めていくので、ウチも気にしません』
そう、真顔で申していたそうです。
潜入させた使用人自ら、
『講師になることで、犯罪の片棒を担ぐことは教員免許を所持している身としては誠に遺憾です。
よって、この場で面接を打ち切らせていただきます』
こう啖呵を切り、件の塾講師になることを拒否した、というオチがございます」
「授業の流れを止めないように気を付けて、
授業終わりに『こう教えると、生徒のモチベーションが上がるアドバイス』をしているらしいんだ。
まぁ、高校生の癖に生意気だって思われるんだろうな。
大体、塾の講師をやっている人は大学生が多いから」
拓実くんの言葉に、反応したのは秋山くんだ。
「ほんと、変わらねーな。
中学校でもそんなだったよ、アイツ。
……教師陣に授業のフィードバックを進んでやるようなやつだった。
それで、経験の少ない新米教師とも馴染んでいたところがあったな。
教師のような年上の人とも、臆せずコミュニケーションが取れる人ですって通知表に書かれていたってことを、本人が言っていたよ」
来る日も来る日も、この状況を何とかするにはどうやって対処をしたらよいか、話し合った。
良い策なんて、高校生が考えることには限界があった。
何も出来ることはないんじゃないか、そんな空気が場を支配することも度々で、皆が途方に暮れた。
そんな空気を破ったのは華恋だった。
「もう去年のことになるけど、中学生の時にからかっていたっていう男の子の話題、多分今となっては道明くんのことだってわかるんだ。
それを深月の前で出したの。
彼女の中でそのことが、トラウマになっていたのに、気付けなかった。
彼女の気分を害してしまったの。
調子に乗ってたところもあった。
親友だから何でも、秘密とかなしで話してくれるはずだって。
話したくないこともあるんだって、そんなことにも気が付かなかった。
だけど、深月がこんな目に遭っているのを見たら、放っておくなんてできなくて。
今はちょっと喧嘩しちゃってるけど、気まずいけど。
ちゃんと深月に謝りたい。
そのためにも、深月を救わなきゃ。
明るい深月に、おはようって言いたいし、笑いかけてほしいの。
だから、皆も部活で忙しいのは分かっているけれど、協力してほしい!」
華恋の訴えに、皆が目線を合わせて、頷いた。
「アイツ、いい友達を持ったな。
俺からも、頼む。
アイツとは、高校も違うから、側にいて守ってやれない。
それが、すごい心苦しいんだ。
俺の分まで、アイツを、深月をよろしく頼む」
秋山くんまで、私たちに頭を下げる。
深月を救う。
そんな思いで一致団結した、そんな矢先に、悲劇は起きた。