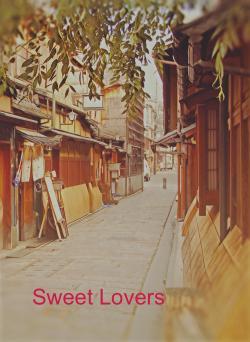涼しい季節は、過ぎるのが早い。
あっという間に、12月になっていた。
ある日、食堂で各々がご飯を食べながら、ガールズトークをしていた。
「椎菜は決めてるの?
麗眞くんへのクリスマスプレゼント!」
「プレゼント、決めてないんだよね。
何でも手に入っちゃうから、何あげればいいか、悩んでて」
華恋の問いに、ビーフシチューを食べる手を止めて俯いてしまう椎菜。
「椎菜自身をラッピングしてさ、
プレゼントは、わ・た・し!
とかやればいいじゃん?
麗眞くんにとっちゃ、どんな料理よりご馳走なんじゃない?」
美冬の一言に一瞬だけ、私たちのテーブルの周囲に冷たい風が吹きすさんだ気がしたのは、気のせいだろうか。
そんな下世話な話題に、いの一番に食いついてきそうな深月の表情が暗い。
文化祭が終わった日から、少し考え込むような表情を時折見せるようになった深月。
彼女のその表情が、気になっていた。
「深月、顔が暗いぞ?
どうしたー?
あ、さては美冬も理名も椎菜もオトコと一緒に過ごすから、それがちょっと悔しいとか?
深月も好きな子、作ればいいのに!
今葉文化祭のシーズンだし、他校の文化祭に足運ぶのもいいかもよ!
中学時代の同級生と高校の文化祭で再会して恋に落ちる、とかいうのもまた一興じゃん?」
その華恋の何気ない一言で、彼女の中でマグマのようにモヤモヤしていたものが、一気に膨れ上がったらしい。
「…………。
絶対行かない!
中学時代の同級生となんて、死んでも会いたくない!
友達はいたけど、親友なんていなかったもん!
私に声掛けてくるのは、下心がある人ばっかりだったわ。
『受験を見据えていい勉強法を教えてほしい』
『一夜漬けでもいいからテストでいい点数を取りたいから暗記系科目のコツを教えてくれ』
とかね。
文化祭なんて行きたくないし、中学時代の同級生が来ていて、どこかですれ違ったのかもしれない、なんて思うだけでも吐き気がする!
実際、中学時代の同級生が後夜祭にいたの。
しかも、心理学心理学うるさいってからかってきた男の子で、顔も見たくない人。
ソイツが休んだ時に、ノート貸したことがあって。
そのときに、柄にもなく丁寧な字でお礼の手紙が挟まってた。
しかも、私が当時好きだったキャラクターの便箋。
ノート貸してくれたお礼だって、学ランの第二ボタンくれたし。
捨てるのは忍びなかったから、今もアルバムと一緒に部屋に飾ってあるけど」
私には分かる。
秋山 道明くんのことだ。
恋愛のカリスマが、決定的なストライクボールを深月に投げた。
こういう話題はお手の物だ。
「深月さ。
他人のことには世話焼くのに、自分のことになるとサッパリね。
少なからず、その人のこと、深月も気になってるんじゃないの?
そうじゃなかったら、学ランの第二ボタンをとっておかないで家に帰ってからゴミ箱に捨てるんじゃない?
その子も、当時は中学生でしょ?
男の子って、その頃は精神年齢が子供だから、からかうしか能がないのよ。
好きな子ほどいじめたくなる、ってやつ」
華恋が何か言いかけたのは、ダン、という机の音で止まった。
「何それ!
私が?
アイツを好き?
有り得ない!
地球の陸と海の割合が逆転するくらい、
ううん、太陽がアンドロメダに近づくくらい有り得ないから!
いい加減なこと言わないで!」
深月は、金切り声でそう吐き捨てて、走って食堂を出て行った。
お昼ご飯は、ほとんど手がつけられていなかった。
本気でキレる深月を、1年近く一緒にいて初めて見た。
私以外の親友たちも、彼女の怒り具合に戸惑っているようだった。
深月がいなくなったのを見計らって、本人には悪いと思ったものの、皆に話した。
あの日、拓実くんの試合の日、カフェで秋山くんから聞いた話だ。
「……ビンゴ。
何よ、実質両想いじゃない。
深月もその、道明くんって子も!
恋愛のカリスマの血が疼くわぁ。
アンタと拓実くんもそうだけど、両想いのくせに気持ちを伝えないっていう恋愛が
一番、燃えるのよねぇ」
深月は、この日以来、私たちの教室に来なくなった。
保健室登校でもしているのだろう。
あっという間に、12月になっていた。
ある日、食堂で各々がご飯を食べながら、ガールズトークをしていた。
「椎菜は決めてるの?
麗眞くんへのクリスマスプレゼント!」
「プレゼント、決めてないんだよね。
何でも手に入っちゃうから、何あげればいいか、悩んでて」
華恋の問いに、ビーフシチューを食べる手を止めて俯いてしまう椎菜。
「椎菜自身をラッピングしてさ、
プレゼントは、わ・た・し!
とかやればいいじゃん?
麗眞くんにとっちゃ、どんな料理よりご馳走なんじゃない?」
美冬の一言に一瞬だけ、私たちのテーブルの周囲に冷たい風が吹きすさんだ気がしたのは、気のせいだろうか。
そんな下世話な話題に、いの一番に食いついてきそうな深月の表情が暗い。
文化祭が終わった日から、少し考え込むような表情を時折見せるようになった深月。
彼女のその表情が、気になっていた。
「深月、顔が暗いぞ?
どうしたー?
あ、さては美冬も理名も椎菜もオトコと一緒に過ごすから、それがちょっと悔しいとか?
深月も好きな子、作ればいいのに!
今葉文化祭のシーズンだし、他校の文化祭に足運ぶのもいいかもよ!
中学時代の同級生と高校の文化祭で再会して恋に落ちる、とかいうのもまた一興じゃん?」
その華恋の何気ない一言で、彼女の中でマグマのようにモヤモヤしていたものが、一気に膨れ上がったらしい。
「…………。
絶対行かない!
中学時代の同級生となんて、死んでも会いたくない!
友達はいたけど、親友なんていなかったもん!
私に声掛けてくるのは、下心がある人ばっかりだったわ。
『受験を見据えていい勉強法を教えてほしい』
『一夜漬けでもいいからテストでいい点数を取りたいから暗記系科目のコツを教えてくれ』
とかね。
文化祭なんて行きたくないし、中学時代の同級生が来ていて、どこかですれ違ったのかもしれない、なんて思うだけでも吐き気がする!
実際、中学時代の同級生が後夜祭にいたの。
しかも、心理学心理学うるさいってからかってきた男の子で、顔も見たくない人。
ソイツが休んだ時に、ノート貸したことがあって。
そのときに、柄にもなく丁寧な字でお礼の手紙が挟まってた。
しかも、私が当時好きだったキャラクターの便箋。
ノート貸してくれたお礼だって、学ランの第二ボタンくれたし。
捨てるのは忍びなかったから、今もアルバムと一緒に部屋に飾ってあるけど」
私には分かる。
秋山 道明くんのことだ。
恋愛のカリスマが、決定的なストライクボールを深月に投げた。
こういう話題はお手の物だ。
「深月さ。
他人のことには世話焼くのに、自分のことになるとサッパリね。
少なからず、その人のこと、深月も気になってるんじゃないの?
そうじゃなかったら、学ランの第二ボタンをとっておかないで家に帰ってからゴミ箱に捨てるんじゃない?
その子も、当時は中学生でしょ?
男の子って、その頃は精神年齢が子供だから、からかうしか能がないのよ。
好きな子ほどいじめたくなる、ってやつ」
華恋が何か言いかけたのは、ダン、という机の音で止まった。
「何それ!
私が?
アイツを好き?
有り得ない!
地球の陸と海の割合が逆転するくらい、
ううん、太陽がアンドロメダに近づくくらい有り得ないから!
いい加減なこと言わないで!」
深月は、金切り声でそう吐き捨てて、走って食堂を出て行った。
お昼ご飯は、ほとんど手がつけられていなかった。
本気でキレる深月を、1年近く一緒にいて初めて見た。
私以外の親友たちも、彼女の怒り具合に戸惑っているようだった。
深月がいなくなったのを見計らって、本人には悪いと思ったものの、皆に話した。
あの日、拓実くんの試合の日、カフェで秋山くんから聞いた話だ。
「……ビンゴ。
何よ、実質両想いじゃない。
深月もその、道明くんって子も!
恋愛のカリスマの血が疼くわぁ。
アンタと拓実くんもそうだけど、両想いのくせに気持ちを伝えないっていう恋愛が
一番、燃えるのよねぇ」
深月は、この日以来、私たちの教室に来なくなった。
保健室登校でもしているのだろう。