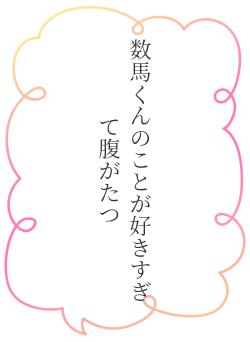私の前に立ち止まった担任の先生は、唇を小刻みにふるわせながら涙を流し、私に小包を1つ渡してきた。
「えっ、なに……」
それは、周翼から掬惠にだった。
涙を次々にこぼす先生から細かい事情の話をきいた。
だから、だから坂口くんは学校にこなかったんだ──。
掬惠の瞳から溢れるように大粒の涙が次々にこぼれ落ちる。
そのまま小包を両手で大切に抱え、階段を一気にかけ降りる。
担任の先生から聞いた話をまだ信じられなくて。
そんなの、信じたくなくて。
「やめて、やめて……、先生それ以上、私、聞きたくないよ──」
絶対に坂口くんがまだどこかにいそうで。
とにかく、校庭まで走り続けた。
だだっ広い校庭、誰もいない、クラブの時によく腰掛けていたベンチにゆっくりと掬惠が涙をぽろぽろ溢しながら座る。
丁寧に包まれた小包の包み紙を順番に開いていく。
中に入っていたのは、坂口くんがよく使い込んで所々ぼろぼろで小さな傷が幾つかある左右揃ったキーパーグローブだった。
「坂口くん、私、ずっと待っていたんだからね………………」
掬惠は周翼のキーパーグローブをぎゅっと抱き締め、肩を振るわせて泣いた。