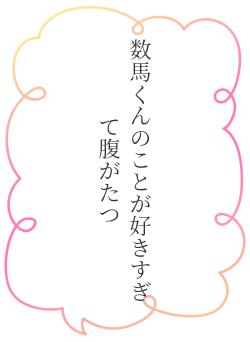溝口先生が連れて行ってくれた焼き肉屋さんのお店で、坂口くんがこっそりとあのくしゃくしゃになったルーズリーフを取り出し綺麗に広げ、小さなボーリングの絵に斜めの線をシュッと書いて潰しているのを私は遠くから見ていた。
夜遅い帰り道、坂口くんと2人きりで帰っている途中、急に気温が下がって寒くなり、白く細かい雪が空から沢山降始めた。
吐く息は白くぼわっと出ては綺麗に消えていく。
「風邪を引いて、喉を痛めるといけないから」と自分が巻いていたマフラーを私の首元に優しく巻いてくれた。
この頃だろか、坂口くんの然り気無い優しさに心が強く引かれていきそうで恐かった。
今、後輩の高谷さんが私達の側にいない。
坂口くんの真っ直ぐに私を見る澄んだ瞳を見る度に、薄く口を開いて『──好きです』って言葉が口から何度も飛び出そうになる。
“好き”って言う言葉は、そう簡単に言える言葉じゃないって、この時に気づいた。
薄々気づいてた、坂口くんのことを好きな後輩の高谷さんを応援しながら、本当は自分も坂口くんのことが好きなんだと──。
今まで、本当の気持ちに蓋をして必死に我慢をしているのがずっと辛かった。
でも、もし私の本当の気持ちを伝えたなら、誰かを酷く傷つけることになってしまうだろう。
そうなったら、後輩の高谷さんが可哀想だ。
私は後輩の高谷さんにあわせる顔がない──。
不意に感情のブレーキが壊れてしまいそうになる自分が時々予告もなくあらわれる。
私も後輩の高谷さんも幸せになる方法はないのだろかとこの時よく悩んだものだった。