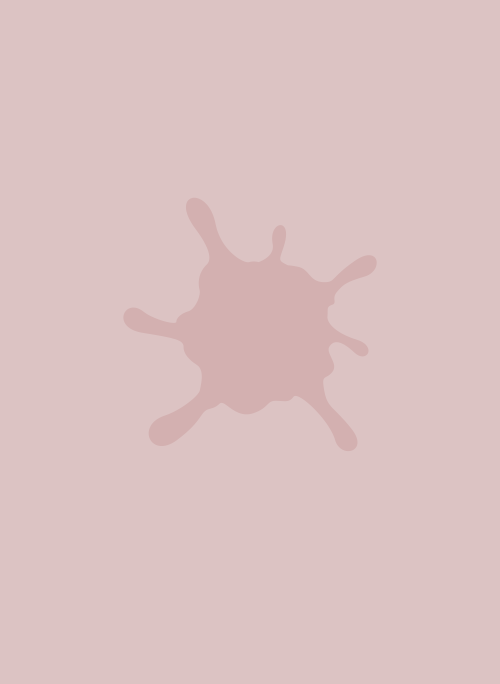とある、休み時間。
あろうことか北見亮がひょこっと私の前に現れた。
なんか、朝のドキドキが湧き上がってくるようだった。
「今朝のケガ、なんともない?」
「うん。大丈夫だよ」
「良かった。無茶はすんなよ」
「ありがとう」
私は声を振り絞るようにしてなんとか言った。
実は、さっき、ありがとうって言えなかったことがかなり気がかりだったのだ。
しかし、いざとなると、急に心拍数が上がって言うのでやっとで、笑顔なんて差し向けられなかった。
そのことでまたちょっと落ち込む。
なんで私、ありがとうって言うだけで緊張したんだろう。
どうして、ドキドキなんかしたんだろう。
そんなつもりないのに。
あろうことか北見亮がひょこっと私の前に現れた。
なんか、朝のドキドキが湧き上がってくるようだった。
「今朝のケガ、なんともない?」
「うん。大丈夫だよ」
「良かった。無茶はすんなよ」
「ありがとう」
私は声を振り絞るようにしてなんとか言った。
実は、さっき、ありがとうって言えなかったことがかなり気がかりだったのだ。
しかし、いざとなると、急に心拍数が上がって言うのでやっとで、笑顔なんて差し向けられなかった。
そのことでまたちょっと落ち込む。
なんで私、ありがとうって言うだけで緊張したんだろう。
どうして、ドキドキなんかしたんだろう。
そんなつもりないのに。