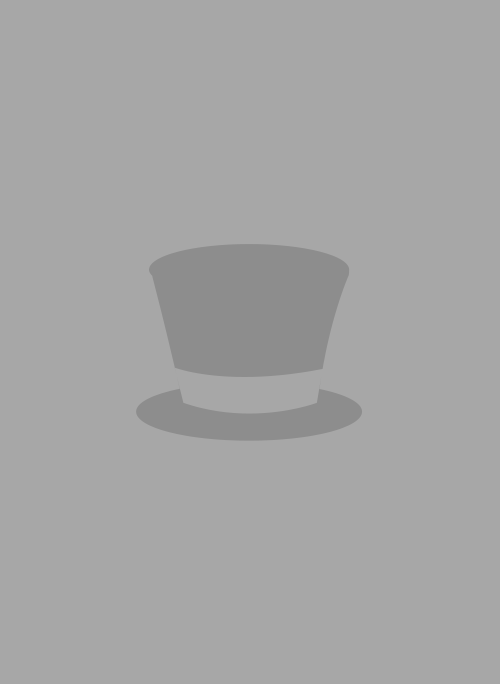それに自分の素性や住所、さらには名前さえ分からなくなっていたというのだ。
…そんな事を信じるお人好しがいるか!?
…まるでギャグの世界だ。
ここはどこ?私は誰?…それとも頭が……?
「もしかして、記憶喪失ってやつか?」
俺は嘲笑気味に言った。
「…そうだと思うの」
彼女は淡い車内灯の中で、俺を真っ直ぐ見つめてきた。
「お願い!助けて」
「助けるったって、どうすりゃいいのよ?」
「…せめて、今晩一晩だけでも泊めて下さい」
「大人をからかうもんじゃないよ」
「そんな、からかうなんて、……」
その時、俺を見つめている眼から、輝く真珠の一粒が生まれた。
俺は女の涙と、理不尽に弱かった。
どちらも理屈では解明できないからだ。
それに、ニュアンスには嘘は感じられなかった。
もしそれが本当の事なら、ソマリアの難民以上に助けを必要としているだろう。
「何か、免許証とかキャッシュカードとか、身分の分かる物を持ってないの?」
「探したんだけど、……見付かったのは、スカートの内ポケットにあった一万円だけだったわ」
俺はこめかみに手を当て、溜め息をついた。
「何故、俺に?」
…そんな事を信じるお人好しがいるか!?
…まるでギャグの世界だ。
ここはどこ?私は誰?…それとも頭が……?
「もしかして、記憶喪失ってやつか?」
俺は嘲笑気味に言った。
「…そうだと思うの」
彼女は淡い車内灯の中で、俺を真っ直ぐ見つめてきた。
「お願い!助けて」
「助けるったって、どうすりゃいいのよ?」
「…せめて、今晩一晩だけでも泊めて下さい」
「大人をからかうもんじゃないよ」
「そんな、からかうなんて、……」
その時、俺を見つめている眼から、輝く真珠の一粒が生まれた。
俺は女の涙と、理不尽に弱かった。
どちらも理屈では解明できないからだ。
それに、ニュアンスには嘘は感じられなかった。
もしそれが本当の事なら、ソマリアの難民以上に助けを必要としているだろう。
「何か、免許証とかキャッシュカードとか、身分の分かる物を持ってないの?」
「探したんだけど、……見付かったのは、スカートの内ポケットにあった一万円だけだったわ」
俺はこめかみに手を当て、溜め息をついた。
「何故、俺に?」