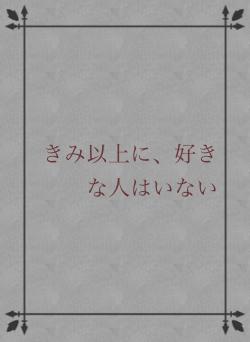離れると、氷野くんはふっとからかうような笑みを見せた。
"かわいい"やキスはくれるのに、肝心の言葉はくれないの?
貪欲になる自分がいることがわかっても、とめられなかった。
「氷野くん、好きです」
「っ、……!」
「氷野くんは……?」
勇気を出してわたしから近づくと、思いっきり顔を背けられた。
でも、その横顔はわたしの何倍もまっかに見えて。
それだけでもう、十分か。
氷野くんが好きで、カレがわたしの想いに応えてくれるなら、なんだっていい。
って、思って離れたのに、その直後。
不器用につむがれた言葉に、わたしはカウンターをくらった気持ちになった。
「……好き、だ」