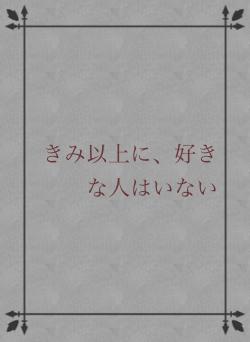必死に言葉をつないで、氷野くんにそう、たずねる。
泣いてしまって、告白の仕方なんてどこかに飛んでいったのかな。
目の前の、氷野くんしか見えなくて。
おでこと頬にされた、キスの余韻にひたる余裕もなくて。
ただ、本心が聞きたくて。
「わたしのこと、好き、ですか……?」
もう一度、言葉にすると、わたしはなんてばかなんだと思った。
こんなの、自惚れもいいところだ。
すると、氷野くんは顔を上げて、かわいく小首をかしげた。
「んー? もものこと好きかって?」
どこまで惑わせるんだ、この男は。
他人事のようにそう思っても、そんな人を好きになってしまったんだから、わたしもたいがいだ。