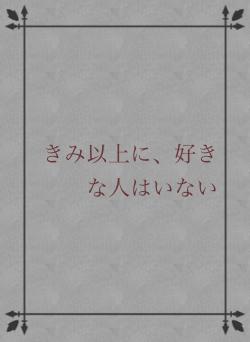「は、入れるの?」
「入れるよ。 俺の穴場」
氷野くんはやわらかく笑って、わたしの手を引く。
腕じゃなくて、手。
手汗かいてないかとか、氷野くんの手って大きいなとか、そんなことを思っては恥ずかしくなる。
でもね、恥ずかしいけど、うれしいんだ。
気を引きしめないと、頬がゆるんでしまうの。
正面で向き合うと、つないでいた手は自然と離れてしまった。
名残惜しい気持ちのわたしを置いて、氷野くんはうすく唇を開いた。
「……で、その格好どうしたの?」
お昼の時間を過ぎて、静かな屋上には誰もいなかった。
文化祭の喧騒が、遠くに感じる。
なんて、ぼんやり考えていたら、氷野くんの言葉に反応が遅れた。