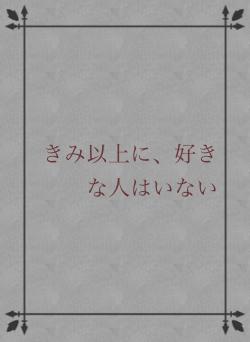好き、って気持ちと同時に切なくなって、わたしはあわてて笑顔をつくった。
このままの、変わらない関係でいたい。
彼女になれないとしても、お隣さんとして笑っていられるなら。
……それで、いい。
「ん、まあ楽しんでくるよ」
氷野くんは、わたしのうしろに隠れていたありちゃんに小さく頭を下げて、階段を下りていった。
な、今のおじぎ! かわいい!
「わっ、なに!」
バッと振り返ると、ありちゃんがびっくりしたように見てくる。
ありちゃんの困惑する表情の前で、うっと顔をしかめるわたし。
「わ、笑えてたかなぁ……」