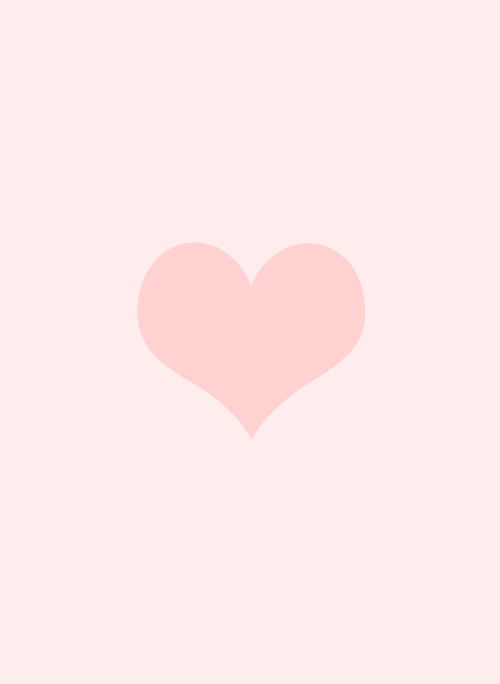上村が指差した先に、花柄の浴衣に真っ赤な金魚の尾ひれような兵児帯を締めた小さな女の子が、木枠に和紙を張った燈ろうを抱えて歩くのが見えた。燈ろうの側面には、可愛らしい猫のイラストが描いてある。
「懐かしい。私も自分で絵を描いた燈ろうを持って、近くの神社の六月灯に行ったな。夜店で母に綿菓子買ってもらうのが楽しみだった」
それはもう遠い記憶だ。夏の宵闇の中を、母と二人手を繋いで歩いた。
神社の入り口の鳥居から境内まで、ろうそくを灯した燈ろうがずらりと下げられていて、夢中になって自分の燈ろうを探した。
あの時も私は、母が仕立てた浴衣を着ていた。一面にピンクの朝顔が散った浴衣は私のお気に入りで、背が伸びて着られなくなった後も、大事に仕舞っておいた。たぶん今も母の部屋に、大切に取ってあるはずだ。
あの頃は、ずっと母といられるのだと思っていた。ずっと母の温かい手を握っていられるのだと信じていた。私はそれを今、失いかけている。
信号が青になり、車が動き出す。私は滲んだ涙を上村に気付かれないように、再び顔を窓の外に向けた。
「懐かしい。私も自分で絵を描いた燈ろうを持って、近くの神社の六月灯に行ったな。夜店で母に綿菓子買ってもらうのが楽しみだった」
それはもう遠い記憶だ。夏の宵闇の中を、母と二人手を繋いで歩いた。
神社の入り口の鳥居から境内まで、ろうそくを灯した燈ろうがずらりと下げられていて、夢中になって自分の燈ろうを探した。
あの時も私は、母が仕立てた浴衣を着ていた。一面にピンクの朝顔が散った浴衣は私のお気に入りで、背が伸びて着られなくなった後も、大事に仕舞っておいた。たぶん今も母の部屋に、大切に取ってあるはずだ。
あの頃は、ずっと母といられるのだと思っていた。ずっと母の温かい手を握っていられるのだと信じていた。私はそれを今、失いかけている。
信号が青になり、車が動き出す。私は滲んだ涙を上村に気付かれないように、再び顔を窓の外に向けた。