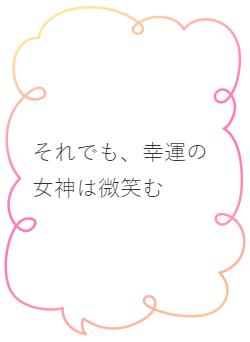――殴って終わりにすればいいのに。
俺はそう思ったけど、あの子の出した答えはそうじゃなかった。
違うんだ。
捨てるか、思い出にしてもっているか。
それは人それぞれなんだ。
そしてたぶん彼女は――
「だからね、たぶん。
私はそういう思いが消えないから、不思議と今も洋介君のこと好きなんじゃないかなって、思う」
――思い出にして、もってるんだ。
いや、もしかしたらまだ思い出にできてはいないのかもしれない。
けど、もってることにしたんだ。
捨てないでいることにしたんだ。
兄貴への恋心とか、思い出とか・・・そういうの。
「だからね、洋介君。
お願い。ちゃんと1人の人と真剣に付き合って?」
真っ直ぐに見つめる瞳。
凛とした澄んだ声。
俺はそう思ったけど、あの子の出した答えはそうじゃなかった。
違うんだ。
捨てるか、思い出にしてもっているか。
それは人それぞれなんだ。
そしてたぶん彼女は――
「だからね、たぶん。
私はそういう思いが消えないから、不思議と今も洋介君のこと好きなんじゃないかなって、思う」
――思い出にして、もってるんだ。
いや、もしかしたらまだ思い出にできてはいないのかもしれない。
けど、もってることにしたんだ。
捨てないでいることにしたんだ。
兄貴への恋心とか、思い出とか・・・そういうの。
「だからね、洋介君。
お願い。ちゃんと1人の人と真剣に付き合って?」
真っ直ぐに見つめる瞳。
凛とした澄んだ声。