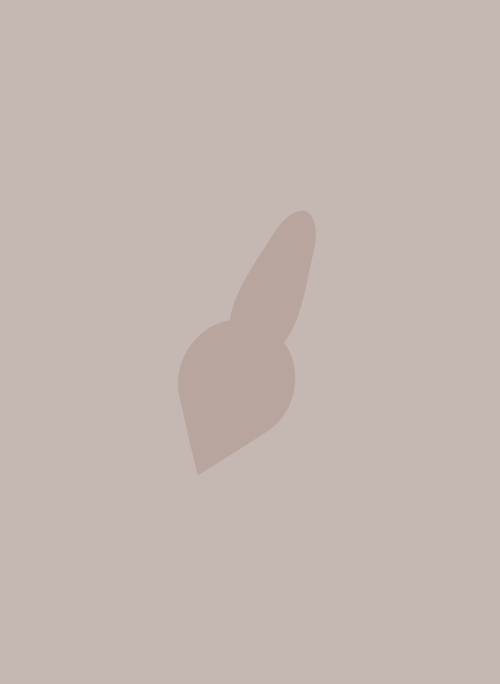洗面所の鏡に、あの女が映っていた。
ワンピースを身につけ、濃い化粧をしたあの女だ。
同じ格好をした剛は、小さく笑い声をあげながら鏡にもたれかかった。女も笑みをうかべながら、こちらにもたれかかってきた。薄いガラス越しに、くっつきあっているような気分だった。
「会いたかったよ」
そう言ってから、いったん鏡をはなれると、声色を変えてこうつぶやいた。
「わたしもよ」
鏡の向こうから、女が話しかけていると思いこみ、剛は幸福感に包まれた。
そのあと何度も声色を変えて、女と会話をかわした。
夢の中での女との思い出について、じっくりと語り合った。
自分が演じているという意識は当然持っていたが、それでも恋い焦がれた女との会話は楽しかった。
ふと思いついて、剛は言った。
「そうだ。おまえに名前をつけないと」
鏡の中の女が首をかしげた。
「名前?」
「そう、名前。おれがおまえのことを、どう呼ぶのかを決めないとな」
「どんな名前にするの?」
「そうだな。何にしようか」
剛はうつむいてだまりこんだ。すると、それを待っていたかのように、頭の中にふたつの漢字がすうと浮かんだ。
「切美だ」
「・・・・・・きりみ?」
「そう、おまえの名前は切美。美しさを切り取ったような姿という意味で、切美だ」
「わたしの名前は、切美」
鏡の中の女、いや、切美は、両手を頬にあてて微笑んだ。名前をあたえたことで、存在感が増したような気がした。同じしぐさをしながら、剛はうっとりとそれを見つめた。