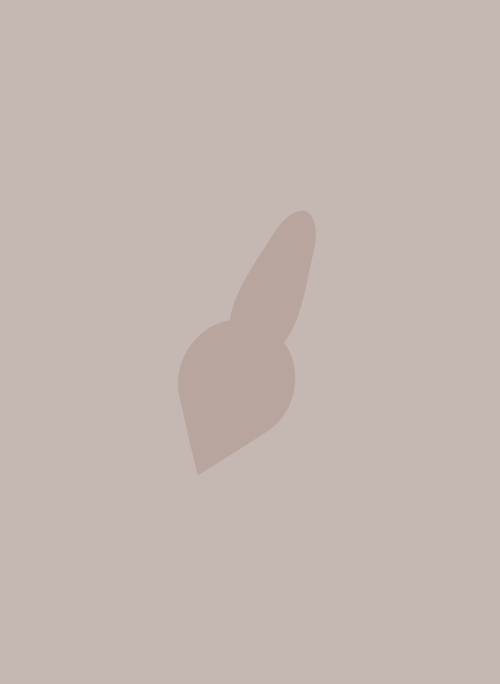洗面所の鏡に、切美が、映っていた。
笑っていた。
剛は何がどうなっているのか、さっぱりわからなかった。夜、いつもどおりに布団で寝ていたのに、目が覚めると、まだ暗い部屋の中、寝間着姿のまま、いつのまにか洗面所の鏡の前に立っていたのだ。
身体の感覚がない。首から上だけが、自由に動かせる。
鏡を見て、剛は目を疑った。
切美の顔に、化粧がほどこされていたのだ。
ありえない。化粧品はすべて処分したはずなのに。
その疑問に答えるかのように、鏡の中の切美は右手を前にさしだした。
それを見て、剛は、ふざけんな、そんなのありかよ、とつぶやき、歯を食いしばった。
右手には、赤と青の色彩ペンが握りしめられていた。机の上のペン立てにさしていたものだ。
切美の化粧は、顔に色彩ペンを塗ったものだったのだ。