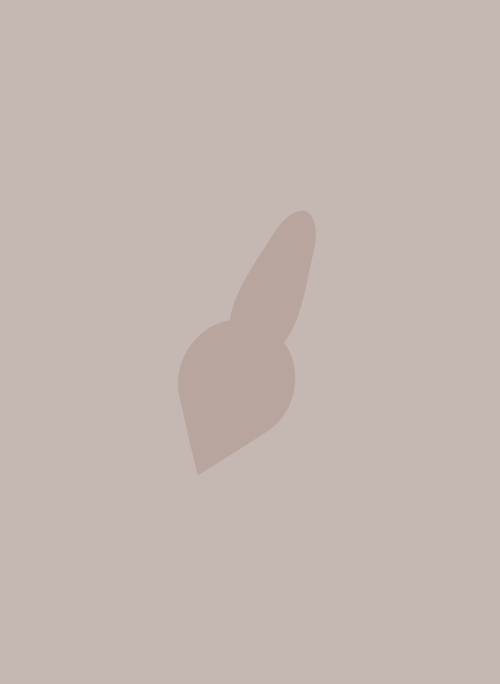「え?」
剛は肩をふるわせた。
「わたしの身体にさわりたくない?」
言葉に誘われるようにして、剛は鏡に映る切美の全身に視線をむけた。
切美の髪、切美の額、切美の眉、切美の目、切美の鼻筋、切美の唇、切美の喉、切美の鎖骨、切美の肩、切美の胸、切美の腹、切美の腰、切美の太腿、切美の脹脛、切美の足の指と爪。
肉体のすべての部位が、自分を呼んでいるような気がして、剛は唾をのんだ。
「さわりたいのね」
切美はうれしそうに言った。
口内がかわくのを感じながら、剛はうなずいた。
「いいわよ。さわらせてあげる」
「でも、どうやって?」
かすれた声で聞く。
「まかせて」
すうっと、剛は身体の感覚がなくなるのを感じた。街にいたときと同じだ。全身を、切美にのっとられた。いや、全身ではない。右手の感覚だけ残っている。右手だけが、剛の意思で動かせる」ようになっている。
意識の中で剛はとまどった。切美はいったい何をしようとしているのか。
「見て」
切美は左手で、着物の裾をそっとつまみあげた。白い片足があらわになった。自分の足ということを完全に忘れて、剛はそれに見とれてしまった。
「さわりたい?」
切美がいたずらっぽく聞いた。首から上ものっとられているので、剛はうなずきたくてもうなずけなかった。返事をしたくても声が出せなかった。それでも欲望を知らせるために唯一うごかせる右手の指を、蜘蛛の足のようにばたつかせた。切美にはそれで伝わったようだった。
「いいわよ。ほら」
右腕がひとりでに動き、剛の右手は切美の太腿に押しつけられた。やわらかい肌に指がめりこんだ。それと同時に、右手の肌だけが異様に紅潮した。むさぼるように、右手は太腿から脹脛、足の先までをいきおいよく這い回った。手のひらににじんだ汗が、足の皮膚にしみこんで、それは這い回った跡ととなり、電灯の光に照らされぬらりと輝いた。やがて右手が太腿の上の方にのぼろうとすると、切美の左手がそれをつかんで足からひきはなした。
「だめ」
切美の左手の中で、剛の右手は不満そうに暴れた。それをやさしくおさえながら、左手は右手を切美の肩の上にのせた。