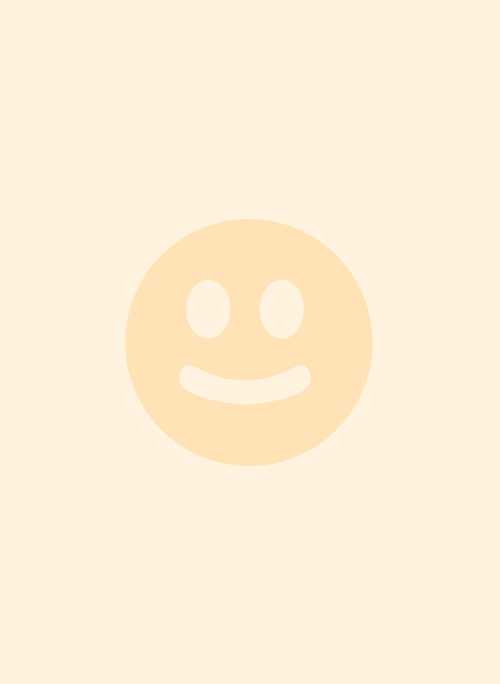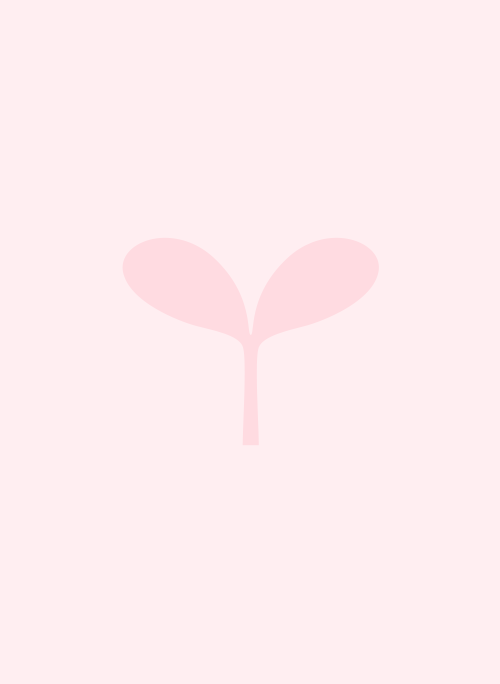「教えて…くれませんか…
どうして…
毎晩俺を訪ねて来たンです…?
水を…使わない日も…あったでしょう?
なのに…ど…して…毎晩…」
「ソージが、そうしてほしそうだったから。」
ダリアは静かに…
けれど子供のように率直に答えた。
「早く帰れ、なんて言ったクセに、ずっと私を見送っていたでしょう?
ほんとは寂しいのカナって思ったの。
違った?」
…
あぁ、もう…
ナニ一つ違ってねェよ、クソが。
やっぱあの時、振り返ったンだ。
やっぱ全部、見抜かれてたンだ。
俺、ダっセ。
まじダっセ。
でも、それでも嬉しかったから。
幸せだって、思えたから。
やっぱ礼を言うのは、俺のほうなんだよ。
「ダリア…
ありがとう…」
本当は、抱きしめたいケド。
白い頬に触れたいケド。
もう身を起こすことはおろか、腕すらも上がらない。
ソージは繋いだ手に残った力を全て込め、強い眼差しでダリアを見上げた。
彼女を、瞳の中に閉じ込めようとするかのように。
刻みつけるかのように。