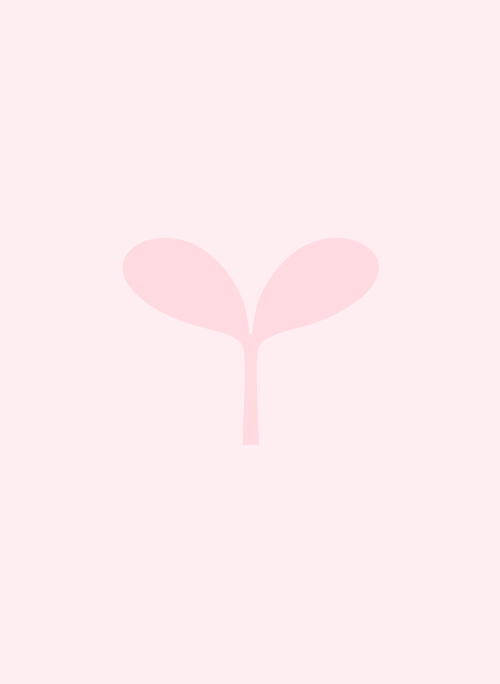「イイの?
ありがとー。」
頬にエクボを作って笑った女が、再びカラカラと釣瓶を引き上げる。
そして丁寧に手を洗う。
ついでに、掌に掬った水を飲む。
(コレ、どーしよ…)
ソージは憑かれでもしたかのように女に見入ったまま、爪で縁側の床板を引っ掻いた。
目が離せない。
脳裏に焼きついてしまう。
彼女の全てが。
唇から零れて顎に伝った水滴ですら、鮮明に。
まじで、どーしよ。
目が離せないってか、目を離したくないンだ。
本当は、もっと傍で見つめてみたいとさえ、思っている。
無理なのに。
近づいてはいけないのに。
なのに、なのに、なのに…
「…
…
…
あの…」
「ん?」
夜に紛れてしまいそうなほどの小さな呼び掛けだったのに、濡れた手をプラプラさせながら女は振り返った。
「また… いつでも来て下さって構いませんよ…
その… 水…使いに…」