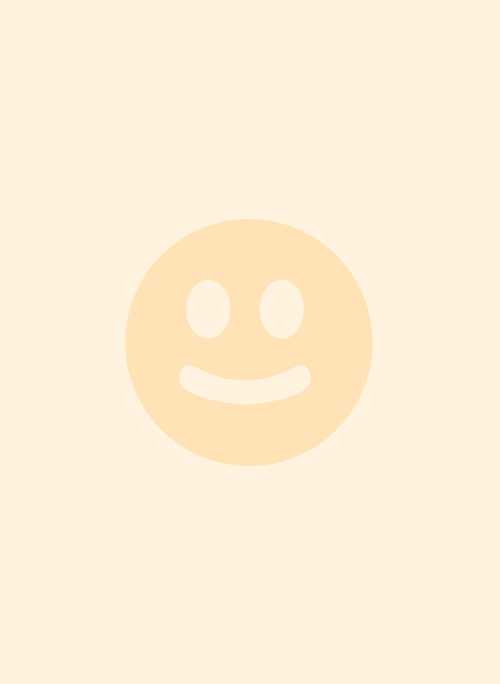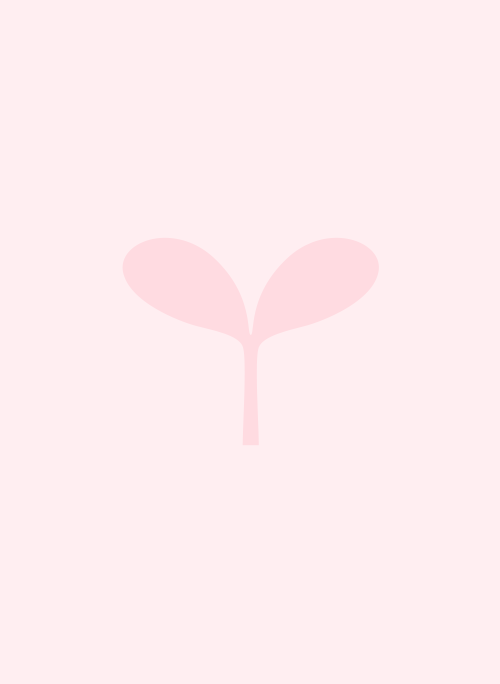「よいしょ。」
一声上げて、バーサンは縁側から立ち上がった。
いつもソージがしていたようにたらいに残った水を庭に撒くと、熱気がほんの少し和らいだ気がする。
あと一ヶ月もすれば暑い夏も過ぎ去り、秋が来る。
この打ち水の涼しさも、きっと忘れてしまうだろう。
「にゃー」
バーサンがたらいを井戸の縁に立て掛けて振り返ると、いつかの黒猫が、またもや鉢植えに前足を伸ばしていた。
「コラ!」
眉を顰めて駆け寄ったバーサンが、一つの鉢を胸に抱いてガードする。
「何度追い払ってもコレだ。
全く、図太い猫だよ。
…
誰かさんみたいだねぇ。」
最後の言葉を口の中で呟いたバーサンは、鉢を抱えたまま視線を上げた。
「旦那ァ…
孫がお世話になりましたねぇ。
代わりと言っちゃナンですが、ここ最近旦那がお気に入りだった鉢植えは、私がちゃんとお世話しますよ。
旦那も、どこかで達者にやって下さいねぇ…」
見上げた青空には、まるで綿菓子のような雲。
彼はきっと生きている。
もう二度と会えない予感はするが、この同じ空の下、きっと図太く生きている。