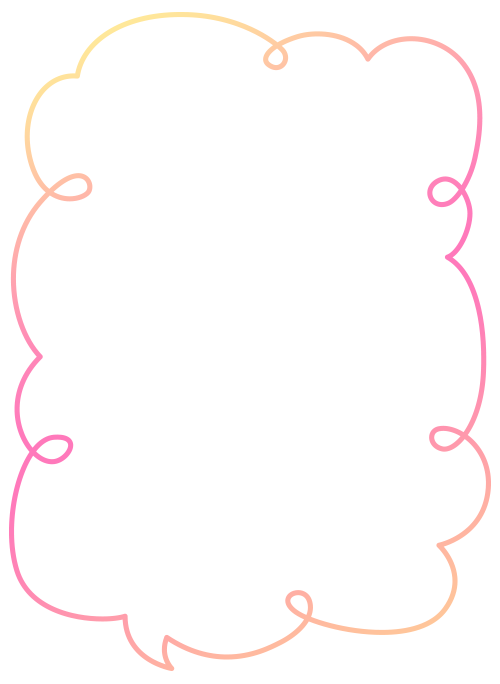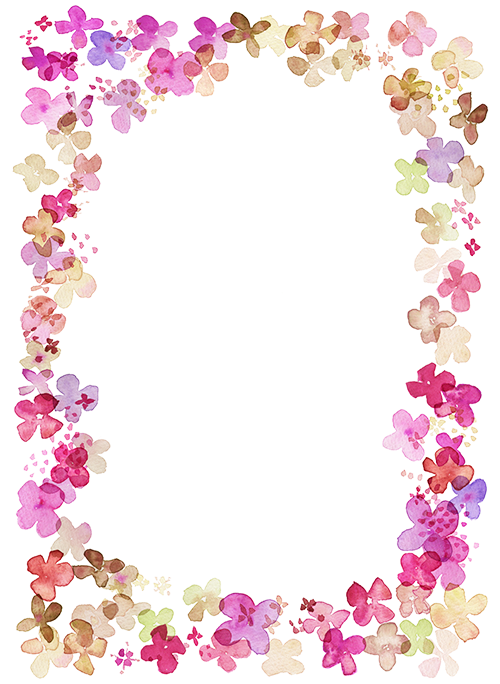「そうよ。高校生にとっては私なんておばちゃんみたいなもんかもしれないけど、私は好きなのよ。大好きなの」
「サトコさんの好きな人って……高校生なんですか?」
「そうよ。いつもすぐそばにいるのに、私……怖くて好きって言えないし。だって、あいつキラキラ輝いてるんだもん。その点、私なんて愛想もなくて可愛くもなくて意地っ張りで素直になれなくて……――」
「ちょっ、サトコさん!!」
テーブルに伏せてしまったサトコさん。
ポンポンッと肩を叩いても、揺すってもサトコさんはピクリとも動かない。
「姫ちゃん、大丈夫。放っておいてあげて」
すると、レオ君はマイクをテーブルの上に置いて苦笑いを浮かべた。