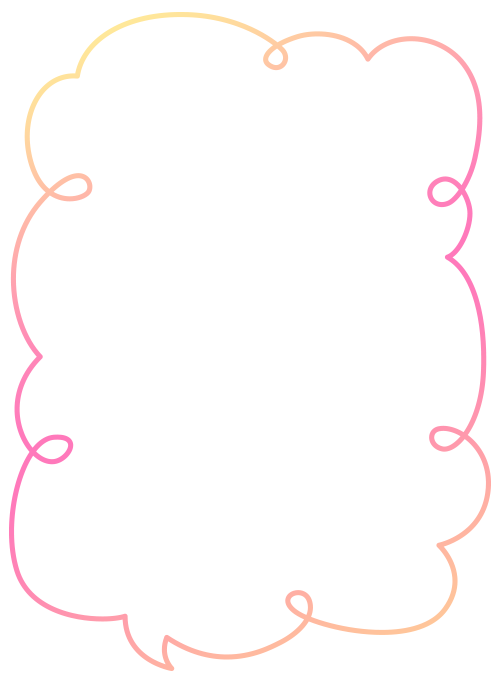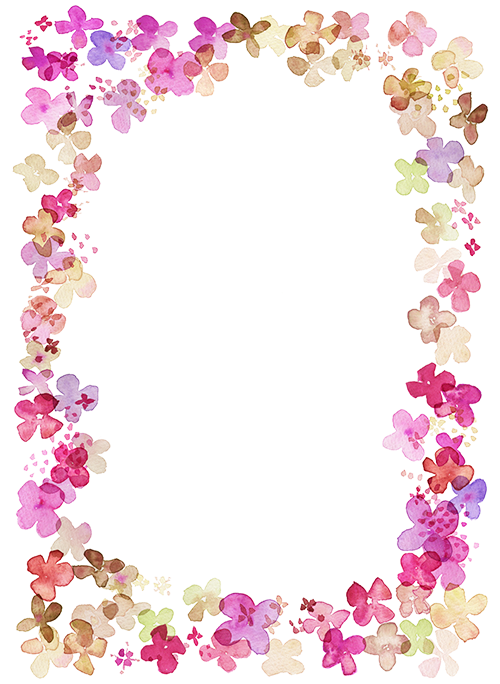「海星君が分かってくれているならそれでいいや」
「お前、甘すぎ。だから、あの女にナメられんだよ」
「いいの。小林さんだけが悪いわけじゃないから。小林さんを止められなかったあたしも悪いし」
「どんだけ良い奴なんだよ」
呆れたように言うと、海星君はギュッとあたしの体に回す腕に力を込める。
そして、耳元でそっと囁いた。
「……――でも、そんなお前だから、好きになったんだろうな」
海星君の優しい声に止まりかけていた涙が溢れる。
「あたしも。こうやって優しい言葉をかけてくれる人だから……海星君を好きになったの」
ギュッと海星君の体にしがみつくと、さっきまでの最低最悪な気分が少しだけ晴れた気がした。