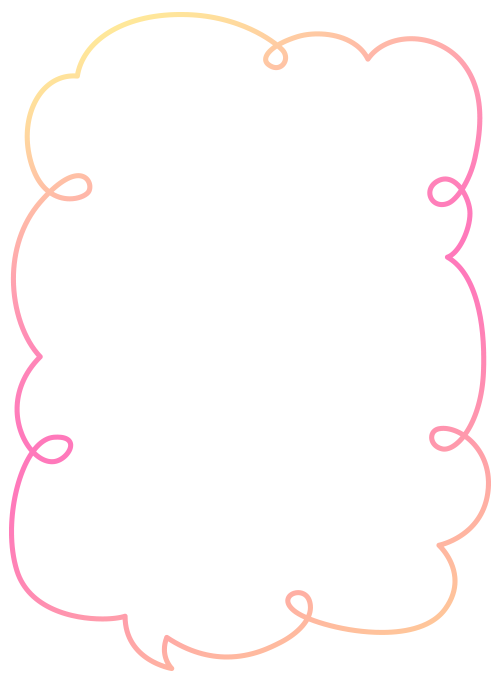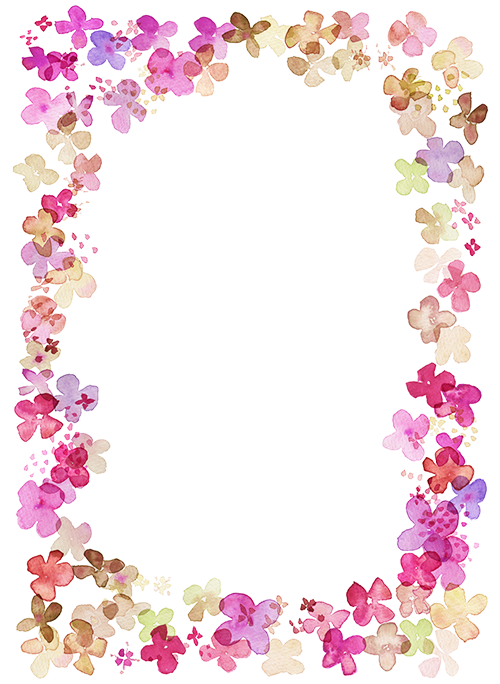「まだ寝てろよ。またぶっ倒れんぞ」
海星君は呆れたように言うと、あたしの肩を支えながらベッドに横になるのを手伝ってくれた。
その時、布団からふわっと漂った甘い香り。
それは、あたしの大好きな海星君の匂いだった。
っていうことは、ま、まさか……。
ここって……海星君の部屋!?
その時、ようやく少し前の出来事を思いだした。
お店から海星君の部屋にたどり着くまでの記憶が一切ない。
「もしかして……あたし……」
「ぶっ倒れるまで我慢すんじゃねぇよ」
海星君はあたしの言葉を遮るようにそう言うと、ハァとため息を吐いた。