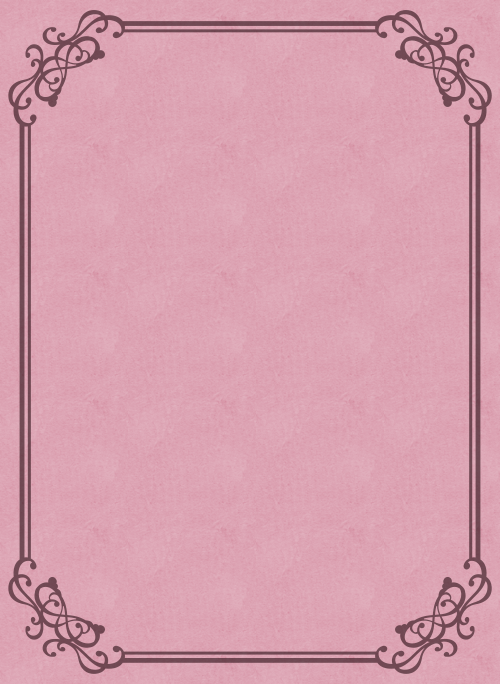「リズ、そちらのお嬢さんは?」
「ああ――、わたしのお友達。領地からこちらに遊びに来ているの。アルマ・シャーレーよ」
「よろしく、アルマ。ダスティ・グレンだ。よろしく」
「……よろしく……お願い……」
うつむき加減にロイは言った。
「僕のことは知らない?」
「そういうわけでも……」
ダスティに顔をのぞき込まれ、ロイは困ったように後ずさった。相手は演技の専門家だ。このまま正面から顔を合わせていたら、気づかれてしまうと思ったのだろう。
「すごく内気な子、なのよ。あなたのファン過ぎて――そんなに正面から見られたら恥ずかしがるわ。あまり困らせないでやって」
エリザベスはあわてて、二人の間に割って入った。この国の若い女性なら、たいていはダスティ・グレンのファンだ。
アルマ――ロイ――の反応があまりにも薄かったので、このままではいぶかしがられてしまうのではないかと不安になったのだ。
「そっか、じゃあ僕はもう行くよ。あちらで何か始まるみたいだし」
エリザベスとロイににこりとして、ダスティは二人から離れていった。
「……ダスティがいるのは誤算だったわ」
ハンドバッグからレースのハンカチを取り出して、エリザベスは額にあてる。
「リズお嬢さんが好きなのは知っていたんですけど。俺興味ないし――何話したらいいものやら」
「俺、じゃないでしょ。わたしと言って」
ロイの言葉をぴしゃりとたしなめておいて、エリザベスは再び広間の中を歩き始めたのだった。
「ああ――、わたしのお友達。領地からこちらに遊びに来ているの。アルマ・シャーレーよ」
「よろしく、アルマ。ダスティ・グレンだ。よろしく」
「……よろしく……お願い……」
うつむき加減にロイは言った。
「僕のことは知らない?」
「そういうわけでも……」
ダスティに顔をのぞき込まれ、ロイは困ったように後ずさった。相手は演技の専門家だ。このまま正面から顔を合わせていたら、気づかれてしまうと思ったのだろう。
「すごく内気な子、なのよ。あなたのファン過ぎて――そんなに正面から見られたら恥ずかしがるわ。あまり困らせないでやって」
エリザベスはあわてて、二人の間に割って入った。この国の若い女性なら、たいていはダスティ・グレンのファンだ。
アルマ――ロイ――の反応があまりにも薄かったので、このままではいぶかしがられてしまうのではないかと不安になったのだ。
「そっか、じゃあ僕はもう行くよ。あちらで何か始まるみたいだし」
エリザベスとロイににこりとして、ダスティは二人から離れていった。
「……ダスティがいるのは誤算だったわ」
ハンドバッグからレースのハンカチを取り出して、エリザベスは額にあてる。
「リズお嬢さんが好きなのは知っていたんですけど。俺興味ないし――何話したらいいものやら」
「俺、じゃないでしょ。わたしと言って」
ロイの言葉をぴしゃりとたしなめておいて、エリザベスは再び広間の中を歩き始めたのだった。