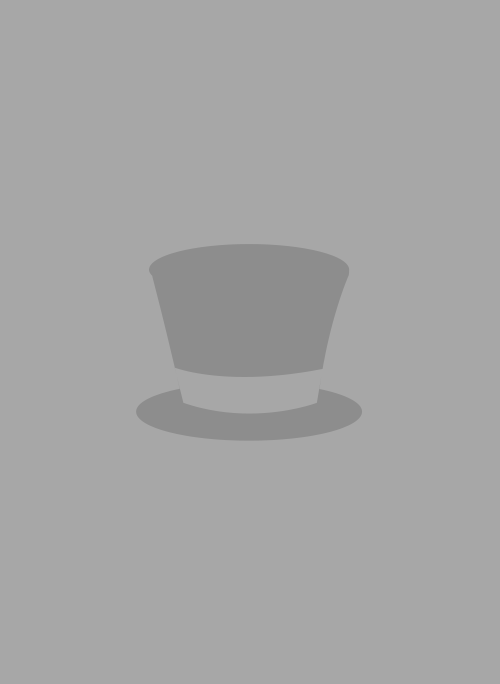僕を支えてくれるのは…飛鳥だ。
いや、飛鳥であってほしい、と言うべきか。
僕の中の雲のような思いは、だんだんとはっきりとしたものになっていた。
「安堂。」
高端の一言で、僕は我に返った。
「ここ、教えてくれる?」
「あ、おう…。」
まだ頭の中の世界に浸っていたかったが、今はそんなことをしている場合ではない。
「ん~、ここはこの構文が使われてるから、ここが関係代名詞だって分かって…。」
教えながら、僕は気づいた。
高端の視線は、問題文ではなく、僕に注がれていた。
「ちゃんと聞いてんのか、高端?」
「き、聞いてるって!」
僕は普通に聞いたのだが、何故か高端は焦ったような、怒ったような口調になっていた。
「…で、ここは…。」
だが僕が説明を始めると、やっぱり高端の視線は僕に注がれる。
「…だから、何で僕を見てんの?」
「ゴ、ゴメン…。」
バイトをしている高端も、僕が今まで見てきた高端とは違っていた。
…もうすぐバラバラになるのが、寂しかったりするのか?…だとしたら、意外とカワイイんじゃん、高端のやつ。
いや、飛鳥であってほしい、と言うべきか。
僕の中の雲のような思いは、だんだんとはっきりとしたものになっていた。
「安堂。」
高端の一言で、僕は我に返った。
「ここ、教えてくれる?」
「あ、おう…。」
まだ頭の中の世界に浸っていたかったが、今はそんなことをしている場合ではない。
「ん~、ここはこの構文が使われてるから、ここが関係代名詞だって分かって…。」
教えながら、僕は気づいた。
高端の視線は、問題文ではなく、僕に注がれていた。
「ちゃんと聞いてんのか、高端?」
「き、聞いてるって!」
僕は普通に聞いたのだが、何故か高端は焦ったような、怒ったような口調になっていた。
「…で、ここは…。」
だが僕が説明を始めると、やっぱり高端の視線は僕に注がれる。
「…だから、何で僕を見てんの?」
「ゴ、ゴメン…。」
バイトをしている高端も、僕が今まで見てきた高端とは違っていた。
…もうすぐバラバラになるのが、寂しかったりするのか?…だとしたら、意外とカワイイんじゃん、高端のやつ。