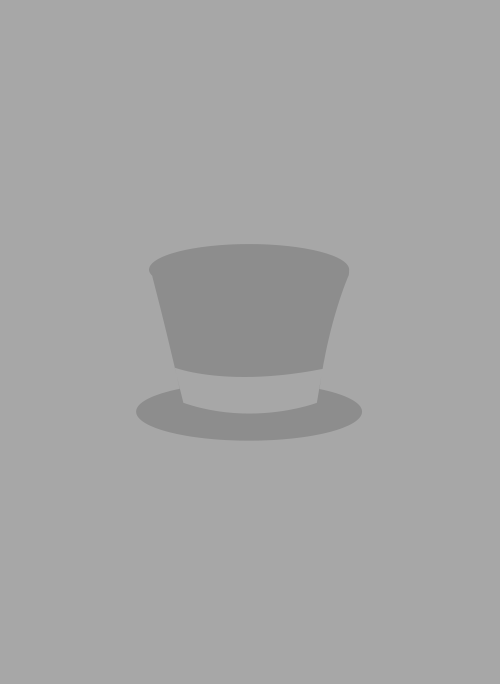朝早く、駅までの道のりを着物姿で歩く飛鳥。
その姿を隣で見ていた僕には、心にはっきりと感じていたものがあった。
それは…恋心。
比較的優しい寒波に乗って飛んできたそれは、僕の心にしがみついて離れなくなっていた。
飛鳥の一挙手一投足が、僕には愛おしかった。
「飛鳥。」
僕は飛鳥の名前を呼んだ。
伝えよう。この思いを。
…だが、僕の心にストッパーを掛けたものがあった。葉月との記憶だ。
僕がこの思いを飛鳥に伝えれば、葉月は果たしてどうなるのだろうか?
嫌いになったわけでもないのに訪れた別れの処理を誤ることにはならないのだろうか?
それが心に引っかかってしまい、僕は口をつぐむしかなかった。
「どうしたんですか?」
…と、飛鳥が尋ねようとも。
その姿を隣で見ていた僕には、心にはっきりと感じていたものがあった。
それは…恋心。
比較的優しい寒波に乗って飛んできたそれは、僕の心にしがみついて離れなくなっていた。
飛鳥の一挙手一投足が、僕には愛おしかった。
「飛鳥。」
僕は飛鳥の名前を呼んだ。
伝えよう。この思いを。
…だが、僕の心にストッパーを掛けたものがあった。葉月との記憶だ。
僕がこの思いを飛鳥に伝えれば、葉月は果たしてどうなるのだろうか?
嫌いになったわけでもないのに訪れた別れの処理を誤ることにはならないのだろうか?
それが心に引っかかってしまい、僕は口をつぐむしかなかった。
「どうしたんですか?」
…と、飛鳥が尋ねようとも。