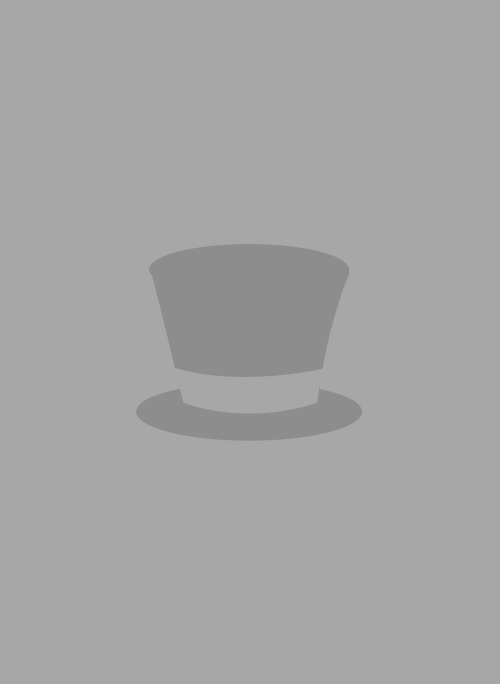「飛鳥!」
飛鳥は…浴槽に入りながら、左手首をナイフで切っていた。ナイフは浴槽の外に転がっており、血が付着していた。妙に血生臭い気がした。
「まさか…。」
僕は飛鳥の右手首に指を当てた。まだわずかながら、脈があるのが確認できた。だが安心できない。いつ手首に脈を感じ取れなくなっても、おかしくない。
「ちょっと待ってろよ…!」
僕は無我夢中で救急車と警察を呼んだ。
「こういう時って何すればいいんだっけ…。」
頭の中で出来る限りの応急処置を考えるが、どれもこういう場合に使える方法じゃない。その間にも飛鳥の左手首からは血が滴り続け、僕の頭は黒く塗りつぶされていく。
「死なないでくれ、飛鳥…!」
僕ができることは、ただ祈ることばかりだった。
十分後、外からけたたましいサイレンの音が聞こえてきた。
「来た!」
僕はドアを全開にした。
「こっちです、こっち!」
僕は一人の刑事さんの腕を引っ張り、風呂場へと連れ込んだ。
「…これは…!」
刑事さんはかなり驚いていた。何故なら、偶然にもその刑事さんは、二宮さんだったからだ。
飛鳥は…浴槽に入りながら、左手首をナイフで切っていた。ナイフは浴槽の外に転がっており、血が付着していた。妙に血生臭い気がした。
「まさか…。」
僕は飛鳥の右手首に指を当てた。まだわずかながら、脈があるのが確認できた。だが安心できない。いつ手首に脈を感じ取れなくなっても、おかしくない。
「ちょっと待ってろよ…!」
僕は無我夢中で救急車と警察を呼んだ。
「こういう時って何すればいいんだっけ…。」
頭の中で出来る限りの応急処置を考えるが、どれもこういう場合に使える方法じゃない。その間にも飛鳥の左手首からは血が滴り続け、僕の頭は黒く塗りつぶされていく。
「死なないでくれ、飛鳥…!」
僕ができることは、ただ祈ることばかりだった。
十分後、外からけたたましいサイレンの音が聞こえてきた。
「来た!」
僕はドアを全開にした。
「こっちです、こっち!」
僕は一人の刑事さんの腕を引っ張り、風呂場へと連れ込んだ。
「…これは…!」
刑事さんはかなり驚いていた。何故なら、偶然にもその刑事さんは、二宮さんだったからだ。