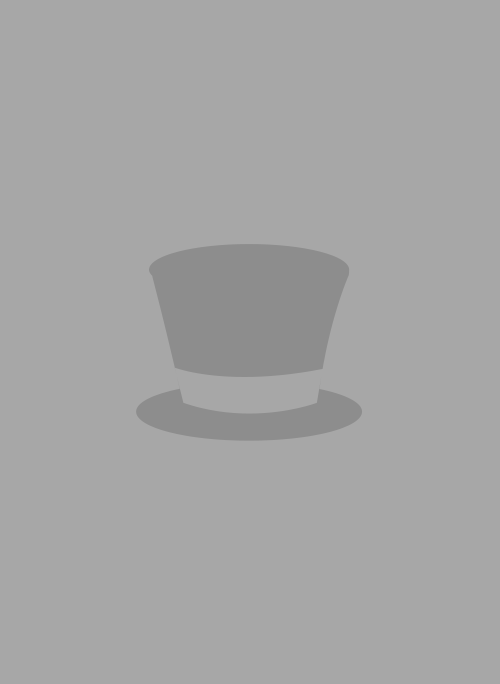「…ゴメン。」
その言葉は、まるで僕の意志を切り捨てたように口から出た。
「えっ…。」
僕は状況を飲みこめていないはずだった。にもかかわらず、僕は断っていた。
「…なるほどね…やっぱりか…。」
高端の方では納得できたらしい。
「…あ、ちょっと友達と約束してたんだった…。ゴメン、もう戻るね。」
高端はデザートのリンゴが二、三切れ入っている弁当箱のふたを閉め、それを持って教室の方へと戻って行った。
不思議と、追いかけようという気持ちにはならなかった。僕は柵の外に広がる街を眺め、ため息をついた。
前なら、僕はここで柵の外に飛び出そうとしていた。でも、そこには「飛鳥が止めてくれるはず」という期待がどこかにあった気がする。
今は、柵の外に飛び出そうとはしていない。でも「飛鳥は来てくれない」ということも分かっている。
僕は今、一人でこうしているしかないのだ。
当たり前のことをこのようにあてもなく想像するようになったのは、飛鳥がいるという状況が、いつの間にか僕の「当たり前」になっていたからなのかもしれない。
「キーン、コーン、カーン、コーン。」
屋上にいても、チャイムは分かりやすいほどに聞こえてくる。僕は一呼吸置いてから、校舎内に続くドアを開け、階段を下った。
飛鳥に、会いたい。
来てくれない、ということが分かって、僕の思いはやっと形を得てきた。
その言葉は、まるで僕の意志を切り捨てたように口から出た。
「えっ…。」
僕は状況を飲みこめていないはずだった。にもかかわらず、僕は断っていた。
「…なるほどね…やっぱりか…。」
高端の方では納得できたらしい。
「…あ、ちょっと友達と約束してたんだった…。ゴメン、もう戻るね。」
高端はデザートのリンゴが二、三切れ入っている弁当箱のふたを閉め、それを持って教室の方へと戻って行った。
不思議と、追いかけようという気持ちにはならなかった。僕は柵の外に広がる街を眺め、ため息をついた。
前なら、僕はここで柵の外に飛び出そうとしていた。でも、そこには「飛鳥が止めてくれるはず」という期待がどこかにあった気がする。
今は、柵の外に飛び出そうとはしていない。でも「飛鳥は来てくれない」ということも分かっている。
僕は今、一人でこうしているしかないのだ。
当たり前のことをこのようにあてもなく想像するようになったのは、飛鳥がいるという状況が、いつの間にか僕の「当たり前」になっていたからなのかもしれない。
「キーン、コーン、カーン、コーン。」
屋上にいても、チャイムは分かりやすいほどに聞こえてくる。僕は一呼吸置いてから、校舎内に続くドアを開け、階段を下った。
飛鳥に、会いたい。
来てくれない、ということが分かって、僕の思いはやっと形を得てきた。