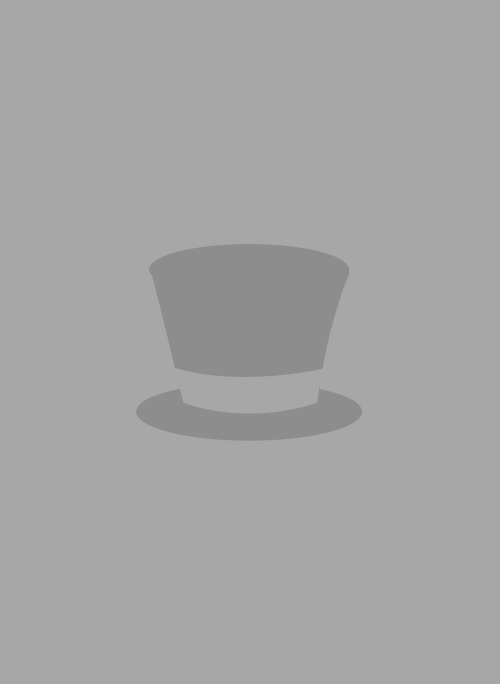結局、飛鳥は文芸部に入ることになった。
「な~んだ、安堂もちゃっかり飛鳥ちゃんを連れ込んでるんじゃん。」
「だから何度も言うけど、僕達は別に…。」
「…顔、真っ赤。」
自覚はなかったが、僕の顔は何故か赤くなってしまっていたらしい。
「さてさて、文化祭も近いし、部誌書いていかないとね。」
僕は前まで書いていた原稿を広げた。だが、何もストーリーが浮かんでこない。いや、前までは確かにストーリが浮かんでいたのに、プロットをなくしてしまったのと、葉月のことに対するショックで忘れてしまった。
「クソ…。」
締め切りまで、あと一週間。こんな所で手が止まることになるなんて…。
「あの…。」
飛鳥が問いかける。
「ここって、小説を書く部活なんですよね…?」
「そうだけど?」
「この紙に、書くんですよね?」
飛鳥が何も書かれていない原稿用紙をひらひらと動かす。
「そう…だけど?」
「ちょっと待ってて下さい。」
すると飛鳥はシャーペンを手に取った。そして次の瞬間、僕達は驚愕の光景を目にした。
「な~んだ、安堂もちゃっかり飛鳥ちゃんを連れ込んでるんじゃん。」
「だから何度も言うけど、僕達は別に…。」
「…顔、真っ赤。」
自覚はなかったが、僕の顔は何故か赤くなってしまっていたらしい。
「さてさて、文化祭も近いし、部誌書いていかないとね。」
僕は前まで書いていた原稿を広げた。だが、何もストーリーが浮かんでこない。いや、前までは確かにストーリが浮かんでいたのに、プロットをなくしてしまったのと、葉月のことに対するショックで忘れてしまった。
「クソ…。」
締め切りまで、あと一週間。こんな所で手が止まることになるなんて…。
「あの…。」
飛鳥が問いかける。
「ここって、小説を書く部活なんですよね…?」
「そうだけど?」
「この紙に、書くんですよね?」
飛鳥が何も書かれていない原稿用紙をひらひらと動かす。
「そう…だけど?」
「ちょっと待ってて下さい。」
すると飛鳥はシャーペンを手に取った。そして次の瞬間、僕達は驚愕の光景を目にした。