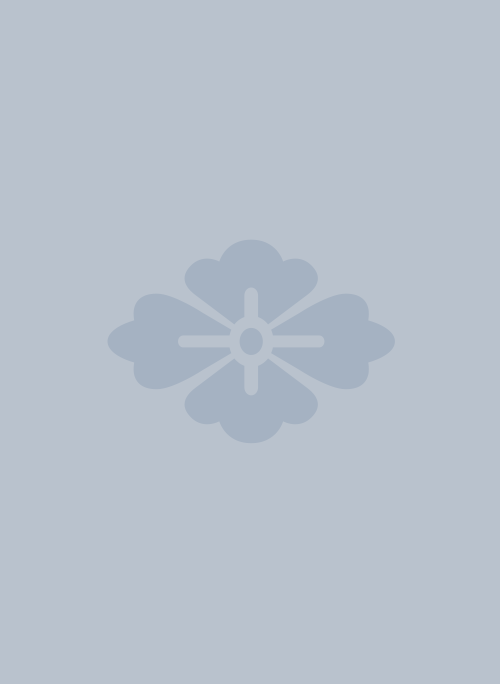言っちゃった……っ!
口に出した瞬間に、後悔が押し寄せる。
これでこのまま本当に私と別れてあの人の所に行っちゃったらどうしよう。
その不安をさらに募らせるかのように、何も言わずに無言で私の腕を引く功希。
どこ行くの、やら離して、やらと声をかけても一切聞いてくれる気配はなく、そのまま家へと着いた私は投げ飛ばされるように家の中へと放り込まれた。
「ちょっ、何すん………っ!?」
靴を履いたまま、玄関先の廊下へと倒れ込んだ私の上へ覆い被さり唇を塞がれる。
押しやろうとしても力の差でどうしても負けてしまう。
私を熟知している功希だから、なおさら。
功希に翻弄された私は、解放されたときには既に体の力が抜けていた。
「口で言っても分からないバカには、体験して覚えて貰うしかないよね」
ぐいっとネクタイを引っ張って緩める功希。
ぼーっとしていた頭は、功希の手が私の洋服のボタンにかけられたところで再び覚醒した。