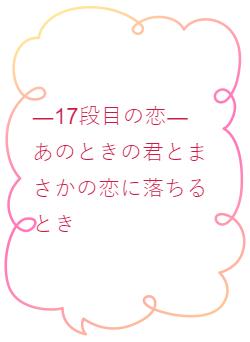「あなたも読んだの?」
「読んだ」
「2冊とも?」
「うん。それも同じ時にね」
凄い偶然だ。
ポケットから手を出して、三品君が右手を差し出す。
「ね、友達になろう。僕たち、気が合うと思う」
「モデルは関係ない?」
「君がシャイラじゃないってことは最初からわかっていた。サイズは一緒だけど、君はシャイラじゃない。僕、一度だけ彼女を見たことがあるんだ。近くにいると感電しそうなくらいオーラがあった。息が止まりそうなほどの強烈なオーラを発していて、もっと近づけたのに、動けなかった」
「一応聞くけど、つまり私にはそのオーラがまったくないと」
「君が、というより、あれは特別な人だけが放つオーラだから、なくて当然だ」
「読んだ」
「2冊とも?」
「うん。それも同じ時にね」
凄い偶然だ。
ポケットから手を出して、三品君が右手を差し出す。
「ね、友達になろう。僕たち、気が合うと思う」
「モデルは関係ない?」
「君がシャイラじゃないってことは最初からわかっていた。サイズは一緒だけど、君はシャイラじゃない。僕、一度だけ彼女を見たことがあるんだ。近くにいると感電しそうなくらいオーラがあった。息が止まりそうなほどの強烈なオーラを発していて、もっと近づけたのに、動けなかった」
「一応聞くけど、つまり私にはそのオーラがまったくないと」
「君が、というより、あれは特別な人だけが放つオーラだから、なくて当然だ」