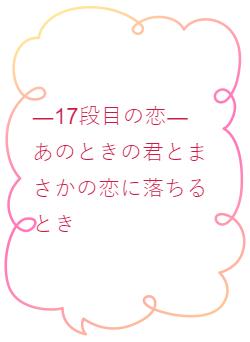「そもそも、バルバリー広告を担当していた僕の師匠から「お前もなんか撮ってみろ」と言われたのが、事の始まりだ。
師匠はどうもバルバリーの広告に乗り気じゃなくて、テスト用に撮り終えた写真を見ながら、「なんかつまんないんだよなー。俺の写真が悪いのか、モデルが悪いのか、バルバリーのコートがつまらないのか」と、何度もぼやいていた。師匠は悪気はないんだけどデリカシーもない。その言葉を聞くたび傍にいたモデルは心を傷め、広報担当者は苦笑いをしていたよ。
で、うだうだと悩んでいた師匠が突然、『そうだ、お前も撮ってみろ。もしお前の写真がよかったら、それでいこう。空いてる時間にこのスタジオ使え。モデルは自分で調達しろ。期限は今週中。ビッグチャンスだ。グッドラック、じゃあな』といって、僕が見る限りでは、いったいどこがつまらないのかわからない、いつもどおりキレのあるポラを撒き散らしたまま帰っていった。
まだ下っ端だったカメラマンの僕に、バルバリーの広告をきめられるモデルの知り合いなんていなかったし、普通ブランドが決めたモデルの契約が途中でひっくり返るはずもない。
どうせ師匠の酔狂なら、ずっと気になっていたアキを撮ろうとそのとき考えた。
アキは大学のカフェで知り合った単なる友人だった。身長が高いわけでもないし、欧米人と比べて彫りが深い顔でもない。だけど出会った時からアキには人を惹きつける不思議な力があると感じていた。
何かわからない磁石みたいな力がね。もしかしたらそれは自分だけが惹きつけられる磁石かもしれない。それでも一度ファインダーから彼女を捉えてみたい、試してみたいと思っていた」
師匠はどうもバルバリーの広告に乗り気じゃなくて、テスト用に撮り終えた写真を見ながら、「なんかつまんないんだよなー。俺の写真が悪いのか、モデルが悪いのか、バルバリーのコートがつまらないのか」と、何度もぼやいていた。師匠は悪気はないんだけどデリカシーもない。その言葉を聞くたび傍にいたモデルは心を傷め、広報担当者は苦笑いをしていたよ。
で、うだうだと悩んでいた師匠が突然、『そうだ、お前も撮ってみろ。もしお前の写真がよかったら、それでいこう。空いてる時間にこのスタジオ使え。モデルは自分で調達しろ。期限は今週中。ビッグチャンスだ。グッドラック、じゃあな』といって、僕が見る限りでは、いったいどこがつまらないのかわからない、いつもどおりキレのあるポラを撒き散らしたまま帰っていった。
まだ下っ端だったカメラマンの僕に、バルバリーの広告をきめられるモデルの知り合いなんていなかったし、普通ブランドが決めたモデルの契約が途中でひっくり返るはずもない。
どうせ師匠の酔狂なら、ずっと気になっていたアキを撮ろうとそのとき考えた。
アキは大学のカフェで知り合った単なる友人だった。身長が高いわけでもないし、欧米人と比べて彫りが深い顔でもない。だけど出会った時からアキには人を惹きつける不思議な力があると感じていた。
何かわからない磁石みたいな力がね。もしかしたらそれは自分だけが惹きつけられる磁石かもしれない。それでも一度ファインダーから彼女を捉えてみたい、試してみたいと思っていた」