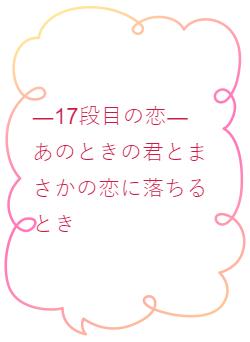「秋・冬用の広告がようやくできた。スカイプしよう」
家に戻り、丁度自分の部屋に入ったところで、リチャードから携帯にメールが届いた。
時間を見ると12時半。ということはニューヨークは夜の11時半になる。
すぐにPCを立ち上げ、スカイプでリチャードに電話をかけた。
電話はすぐにキャッチされ、リチャードとティムさんまでもがモニターに写って現れた。
「はっろ~」
2人とも上機嫌だ。
「こんな時間に2人で何やってるの?」
「一緒に食事して、そのあと僕のオフィスで上がったばかりのケルメスの広告を見てたんだよ」
確かリチャードのオフィスは72丁目のレキシントンアヴェニューだったかな、とおしゃれなカフェやレストランが並ぶマンハッタンのアッパーウエストサイドの町並みを思い浮かべた。
「で、ど、どう?」
「ど、どう? ってどう言う意味だ」
「いや、うまくいったかとちょっと心配で言葉が詰まったの」
「最高だ。俺の写真も素晴らしいが、サキも素晴らしい」
モニターにリチャードが乗り出してきた。
「やっぱり血、なのかしら?」
その肩越しにティムさんが右手の小指を口もとに立て、首をかしげた。
「どういうこと?」
リチャードとティムさんが顔を見合わせた。
「サキのママは僕にとって最初のモデルで運命の女神。知らない?」
「知らない!」
「ウソ! あんたのママ、一時カリスマモデルだったのよ」
家に戻り、丁度自分の部屋に入ったところで、リチャードから携帯にメールが届いた。
時間を見ると12時半。ということはニューヨークは夜の11時半になる。
すぐにPCを立ち上げ、スカイプでリチャードに電話をかけた。
電話はすぐにキャッチされ、リチャードとティムさんまでもがモニターに写って現れた。
「はっろ~」
2人とも上機嫌だ。
「こんな時間に2人で何やってるの?」
「一緒に食事して、そのあと僕のオフィスで上がったばかりのケルメスの広告を見てたんだよ」
確かリチャードのオフィスは72丁目のレキシントンアヴェニューだったかな、とおしゃれなカフェやレストランが並ぶマンハッタンのアッパーウエストサイドの町並みを思い浮かべた。
「で、ど、どう?」
「ど、どう? ってどう言う意味だ」
「いや、うまくいったかとちょっと心配で言葉が詰まったの」
「最高だ。俺の写真も素晴らしいが、サキも素晴らしい」
モニターにリチャードが乗り出してきた。
「やっぱり血、なのかしら?」
その肩越しにティムさんが右手の小指を口もとに立て、首をかしげた。
「どういうこと?」
リチャードとティムさんが顔を見合わせた。
「サキのママは僕にとって最初のモデルで運命の女神。知らない?」
「知らない!」
「ウソ! あんたのママ、一時カリスマモデルだったのよ」