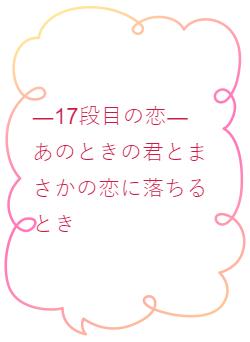何も知らなかったのんきな私。
「ごめんね、トオ兄」
私は幼い頃のトオ兄に謝った。
話し終わった後、外をぼんやり見つめていたトオ兄が、驚いた様子で私を振り向いた。
「なんでお前が謝るんだ」
涙がこぼれた。一旦こぼれた涙はどうにも止まらなくなって、私はシャクリを上げた。
外の街灯が滲んでぼんぼりになっていた。
「だから、なんで泣くんだよ。まるで俺が泣かしてるみたいじゃないか」
目の前にあったペーパーナフキンで、トオ兄が慌てて私の涙をぬぐってくれた。さっき口を拭いたやつだから、生クリームのバニラの香りがした。
「確かに気付くのが遅すぎるが、謝らなくてもいい」
いや、そういうつもりで謝っているわけではなくて。
「俺の顔は外国人が混ざってるから、咲季が小学生になったらきっと不思議に思うだろうと心配してたんだ。
でもお前はまったく疑問に感じてなかった。
それでも中学生になったらさすがにわかるだろう、そしたら咲季にちゃんと説明しようってパパとママとも話していた。けど、いつまでたっても気付く気配はないし、それどころか『トオ兄ってハーフみたいだね』なんてとんまなことを言ってるからみんな気が抜けて、放っておくか、ってことになったんだよ。
でもこのままいくと多分、お前はずーっと気付かなくて、他の誰かから言われて気づくという嫌なパターンになるんじゃないかと、それだけが心配だった」
「もしかしてアルバムも……」
「ごめんね、トオ兄」
私は幼い頃のトオ兄に謝った。
話し終わった後、外をぼんやり見つめていたトオ兄が、驚いた様子で私を振り向いた。
「なんでお前が謝るんだ」
涙がこぼれた。一旦こぼれた涙はどうにも止まらなくなって、私はシャクリを上げた。
外の街灯が滲んでぼんぼりになっていた。
「だから、なんで泣くんだよ。まるで俺が泣かしてるみたいじゃないか」
目の前にあったペーパーナフキンで、トオ兄が慌てて私の涙をぬぐってくれた。さっき口を拭いたやつだから、生クリームのバニラの香りがした。
「確かに気付くのが遅すぎるが、謝らなくてもいい」
いや、そういうつもりで謝っているわけではなくて。
「俺の顔は外国人が混ざってるから、咲季が小学生になったらきっと不思議に思うだろうと心配してたんだ。
でもお前はまったく疑問に感じてなかった。
それでも中学生になったらさすがにわかるだろう、そしたら咲季にちゃんと説明しようってパパとママとも話していた。けど、いつまでたっても気付く気配はないし、それどころか『トオ兄ってハーフみたいだね』なんてとんまなことを言ってるからみんな気が抜けて、放っておくか、ってことになったんだよ。
でもこのままいくと多分、お前はずーっと気付かなくて、他の誰かから言われて気づくという嫌なパターンになるんじゃないかと、それだけが心配だった」
「もしかしてアルバムも……」