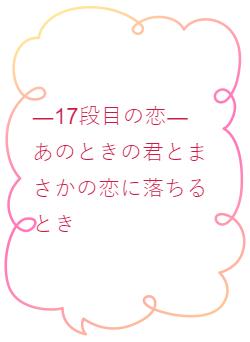「トオル、トオル」って俺を呼ぶ声が母さんの最後の言葉だ。
父さんは警察に連行されたあと、薬の過剰摂取で発作を起こして刑務所に入る間もなく死んだ。
ママは真っ白いシャツを真っ赤に染めて、血だらけの腕で、やっぱり血だらけになって立ちすくんでいた俺を『大丈夫。私が守ってあげる。守ってあげるから』って言って抱きしめてくれたんだ。
というわけで、本当の両親が死に、それから俺はママの子供になった」
これはしげるさんから後で聞いたことだが、トオ兄はこの時もこの後も、ずっと泣くことはなかったそうだ。
まるで悲しいとか辛いとか、痛いとか、そんな感情をジップロックに詰め込んで、体の中に押し込めてしまったようだと語っていたしげるさんの方が、いかつい顔をくしゃっとさせて、
「まだ小さな子供だったのに不憫だわ」と、小さい目からぽろぽろ涙をこぼしていた。
私のせいでトオ兄は、ずっと封印してきた思い出したくない過去を目の前で引きずり出している。
私が知りたかったこと、明らかにしようとしたことは、トオ兄が忘れようとしていたはずのことなのに。
いや、もしかしたらきっとこれまでも、忘れたいのに私を見るたび思い出さずにはいられなかったのかもしれない。
私が生まれた時、トオ兄はどんな気持ちだったのだろう。
私が生まれてきたことで、血のつながりを意識して寂しくなったことはないだろうか。
当時、まだ失ったばかりの家族を思いだし、恋しくなったりしなかっただろうか。私には想像もつかないそんな思いと、まだ幼かったトオ兄はどんなふうに折り合いをつけ、胸の中にたたみ込んできたのか。
私が思い描いた幼いころのとお兄の姿は切なくて、みぞおちに落ちた錘がふるふると震えだしてくるようだった。
父さんは警察に連行されたあと、薬の過剰摂取で発作を起こして刑務所に入る間もなく死んだ。
ママは真っ白いシャツを真っ赤に染めて、血だらけの腕で、やっぱり血だらけになって立ちすくんでいた俺を『大丈夫。私が守ってあげる。守ってあげるから』って言って抱きしめてくれたんだ。
というわけで、本当の両親が死に、それから俺はママの子供になった」
これはしげるさんから後で聞いたことだが、トオ兄はこの時もこの後も、ずっと泣くことはなかったそうだ。
まるで悲しいとか辛いとか、痛いとか、そんな感情をジップロックに詰め込んで、体の中に押し込めてしまったようだと語っていたしげるさんの方が、いかつい顔をくしゃっとさせて、
「まだ小さな子供だったのに不憫だわ」と、小さい目からぽろぽろ涙をこぼしていた。
私のせいでトオ兄は、ずっと封印してきた思い出したくない過去を目の前で引きずり出している。
私が知りたかったこと、明らかにしようとしたことは、トオ兄が忘れようとしていたはずのことなのに。
いや、もしかしたらきっとこれまでも、忘れたいのに私を見るたび思い出さずにはいられなかったのかもしれない。
私が生まれた時、トオ兄はどんな気持ちだったのだろう。
私が生まれてきたことで、血のつながりを意識して寂しくなったことはないだろうか。
当時、まだ失ったばかりの家族を思いだし、恋しくなったりしなかっただろうか。私には想像もつかないそんな思いと、まだ幼かったトオ兄はどんなふうに折り合いをつけ、胸の中にたたみ込んできたのか。
私が思い描いた幼いころのとお兄の姿は切なくて、みぞおちに落ちた錘がふるふると震えだしてくるようだった。