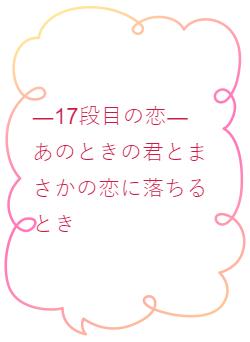明美さんはお茶をすすりながら、斜め45度の目線で私をじとっと見ている。
「あんたさあ、本当にじれったい子ねえ。なんか私に聞きたいことがあるんでしょ」
う、はっきり言われてなおさらひるむ。
自分の部屋なのに、ものすごく苦手な先生の説教部屋にいるような緊張感だ。
「明美さん、迫力ありますね」
全然、関係ないことは口から勝手にポロリとこぼれる。
ふん、と明美さんが丸くてちっちゃい鼻からあきれたように息を吐いた。
「用事がないなら、もう帰るわよ。一人で外なんて出るんじゃないわよ。店の番号は知ってるわよね」
しびれを切らしたように早口でそう言うと、明美さんは残りの紅茶を一気にすすって、椅子から立ち上がった。
まずい。これではせっかくここまで明美さんを呼び出した意味がない。
慌てて「明美さんはママがニューヨークに来たばかりのころからの知り合いだよね。トオ兄は、トオ兄は……」と、やっとのことで説明し始めたところで、チャリラリラララ~と軽やかな音楽が小さく鳴り響き、あ、ちょっとごめんと、明美さんはジャケットのポケットから携帯を取り出した。そして「あ、はいはい。あ、そう。オッケー。了解」と、それだけ言って電話を切ると、再び椅子に腰を下ろした。
どうやら話の続きを聞いてくれるようだ。
「あんたさあ、本当にじれったい子ねえ。なんか私に聞きたいことがあるんでしょ」
う、はっきり言われてなおさらひるむ。
自分の部屋なのに、ものすごく苦手な先生の説教部屋にいるような緊張感だ。
「明美さん、迫力ありますね」
全然、関係ないことは口から勝手にポロリとこぼれる。
ふん、と明美さんが丸くてちっちゃい鼻からあきれたように息を吐いた。
「用事がないなら、もう帰るわよ。一人で外なんて出るんじゃないわよ。店の番号は知ってるわよね」
しびれを切らしたように早口でそう言うと、明美さんは残りの紅茶を一気にすすって、椅子から立ち上がった。
まずい。これではせっかくここまで明美さんを呼び出した意味がない。
慌てて「明美さんはママがニューヨークに来たばかりのころからの知り合いだよね。トオ兄は、トオ兄は……」と、やっとのことで説明し始めたところで、チャリラリラララ~と軽やかな音楽が小さく鳴り響き、あ、ちょっとごめんと、明美さんはジャケットのポケットから携帯を取り出した。そして「あ、はいはい。あ、そう。オッケー。了解」と、それだけ言って電話を切ると、再び椅子に腰を下ろした。
どうやら話の続きを聞いてくれるようだ。