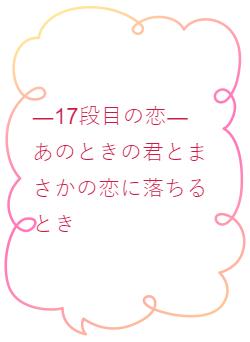2人で店を出る。
夜になってさすがに昼間の暑さは引いていたが、それでもビルの合間にこもった熱気は未だに出口が見つからないようで、ぬるい空気が体にまとわりついてきた。
夜だけど落ち着くからと、サングラスをかけた明美さんはいかにもニューヨークの女って雰囲気を醸し出していた。
颯爽と歩く姿を見たかったのに、お店の前ですぐにイエローキャブを捕まえた。
ドアを開けてまず私を車内に押し込んでから自分も体を入れて、勢いよくバシッとドアを閉めた。
「歩かないの?」
「最近、ひったくりとか多いのよ。それにあんたと並んで歩いたら私が異様にちびで太って見えるじゃない」
「明美さんもそういうの、気になる?」
「いや、本当のこと言うと、このヒールじゃかったるくてホテルまで歩けない」
華奢なベルトのサンダルを片方脱いで、私の前で振ってみせた。かかとから伸びている細いヒールの高さは15センチはあるだろう。
「もしかして買ったばかり?」
「ピンポーン。奮発してジミー・チューのを買ってみたんだけどさあ、所詮カラダの作りは男じゃない? 小柄といえども足の幅が広いのよ。もー、窮屈だし、この体を支えるのも大変。こんなヒールで優雅に歩くモデルってやっぱりすごいわねえ」
夜になってさすがに昼間の暑さは引いていたが、それでもビルの合間にこもった熱気は未だに出口が見つからないようで、ぬるい空気が体にまとわりついてきた。
夜だけど落ち着くからと、サングラスをかけた明美さんはいかにもニューヨークの女って雰囲気を醸し出していた。
颯爽と歩く姿を見たかったのに、お店の前ですぐにイエローキャブを捕まえた。
ドアを開けてまず私を車内に押し込んでから自分も体を入れて、勢いよくバシッとドアを閉めた。
「歩かないの?」
「最近、ひったくりとか多いのよ。それにあんたと並んで歩いたら私が異様にちびで太って見えるじゃない」
「明美さんもそういうの、気になる?」
「いや、本当のこと言うと、このヒールじゃかったるくてホテルまで歩けない」
華奢なベルトのサンダルを片方脱いで、私の前で振ってみせた。かかとから伸びている細いヒールの高さは15センチはあるだろう。
「もしかして買ったばかり?」
「ピンポーン。奮発してジミー・チューのを買ってみたんだけどさあ、所詮カラダの作りは男じゃない? 小柄といえども足の幅が広いのよ。もー、窮屈だし、この体を支えるのも大変。こんなヒールで優雅に歩くモデルってやっぱりすごいわねえ」