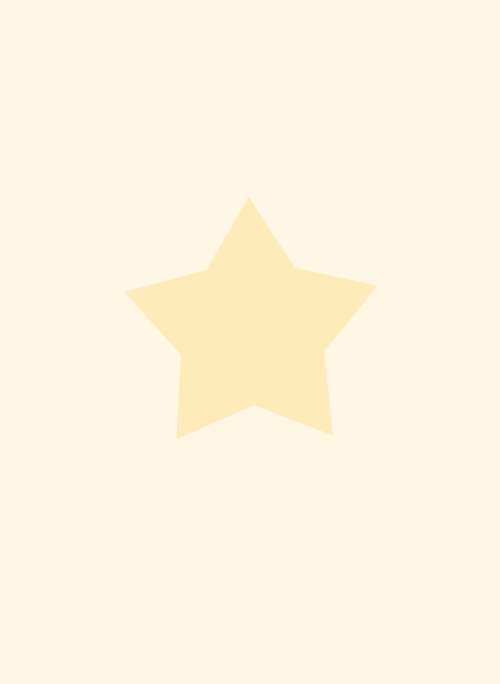「…考えてみると、人生というのもまた、夢の続きなのかもしれぬ…」
次の日、去り際に言われた言葉が気になりつつも、いつものようにその人の話を聞いていた。
「寝ても覚めても同じことしか起こらぬ、同じものしか見えぬ………なぁ君、こんな人生はずっと夢を見ているのと同じじゃないかね?」
語る声音は、いつもより悲しげで、その人を見詰めると、視線があった。
普段本を見詰めながら問うその人は、今はっきりと此方を見詰め、此方の答えが出るのを待っている。
…ずっと、ずっと問いに答えられず、その人の言葉を、その人の言葉のみを聞いていたが、自らの答えを、自らの言葉を、発することはなかった。
「…」
「どうかね?」
見詰める瞳は真剣そのもので、告げる声音は何処か儚さと憂いを帯びている。
「私の人生は、まるで夢じゃないかね?」
それだけ告げ、その人は満足そうに部屋を出て行く。
机の上に広げられていた本は、いつの間にかひとりの青年とひとりの老人がいるだけの、写真集になっていた…。