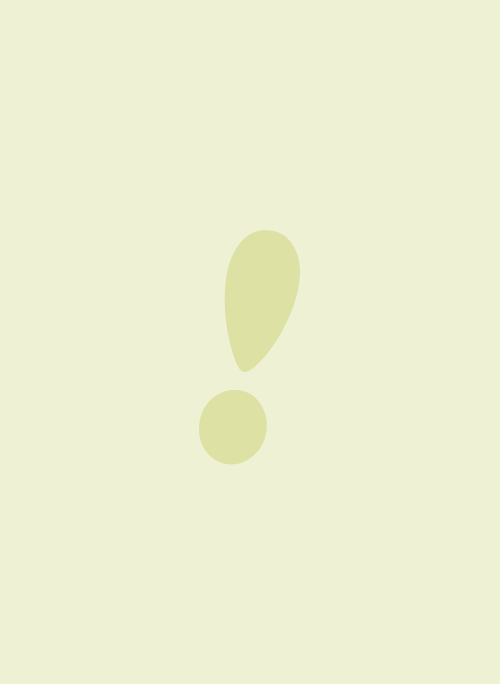──それから、自分がどうしたのか覚えていない。
ただ、なぜか、爽汰の家のソファーに座っている。
キッチンでは、爽汰が紅茶を汲んでいる。
香りから察するに、あたしが唯一飲める紅茶、苺紅茶。
どんないい香りでも、どんなに高い紅茶でも、独特の苦味? というか──紅茶そのものの味が嫌いだったんだけど、あのメーカーの苺紅茶は、甘ったるいぐらい甘くて美味しいんだ。
まぁ、爽汰は甘すぎて飲めないって顔を歪めていたけど。
「ほい、藍羅」
そうこうしているうちに、爽汰がティーカップを持って隣に座る。
受け取って口をつけると、程良い暖かさ。
むしろ、普通の人にはぬるいかもしれない。
あたしが猫舌なの、爽汰は知ってるからだ。