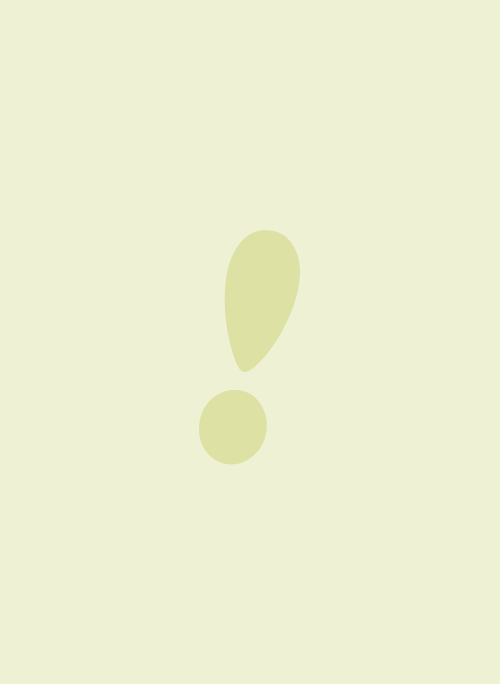あたしの頭には、不安しかない。
野村の言っていることが「真実」っていう証拠はないから。だから──
「ごめん、野村。彼氏、待ってるから、行く」
これ以上、野村が何かを思い出す前に。
これ以上、野村が何かを言う前に。
私は、逃げ出した。爽汰のもとへ。
「あ、藍羅!」
「……なに?」
「忘れもん」
────手渡されたのは、リップクリーム。
「ホテルの部屋に、落ちてた」
ドクリ。
心臓が、嫌な感じに脈打った。
一ミリも動けず目を見開くしかできないあたしの耳に、クスリと笑った彼の声が届く。
「じゃーな」
ぽんっと頭を叩かれた感触が、気持ち悪くてたまらなかった──。